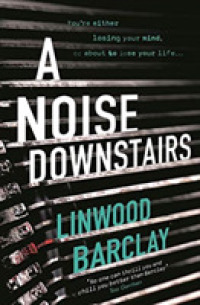感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のぶのぶ
13
AさせたいならBと言え、私もいろいろ自然と使っている。我がオリジナルもいくつかある。数、色、音、場所などゆらぎないものを入れて指示や発問すると、子どもの知的な思考を刺激できるようだ。新人さんと仕事をしているので、まず指示の出し方かなあと思い、積ん読していたものを手に取ったら面白くて一気読み。とても参考になった。○の○の○作文は、実践してみます。数、色の読み取りも実践したい!!2015/05/02
ルル
7
知的に動かしたいなら、知的な発問や知的な指示が必要!いかに自分が知的でないな、を確認できました(>_<)2015/12/23
みつ
5
「ごみを拾いなさい」という指示と「ごみを10個拾いなさい」という指示はどちらが子どもに通りやすいか。「喉を開けて歌いなさい」と「マシュマロをかまずに丸ごと飲み込む感じで歌いなさい」という指示ではどちらが効果的か。ということについて述べられている教育技術書。【言葉の中に小さな特異点を示すと、子どもの心は動く】2011/02/27
るい
4
「おへそをこちらへ向けなさい。」という指示で、前を向かせる。「前を向きなさい。」「こちらを見なさい。」と直接言わなくても、生徒をより的確に動かすことができる。「AさせたいならBと言え。子どもに指示する際、いつも念頭に置いておきたい言葉である。この原則で、子ども達を知的に動かすことができる。子ども達は知的に動くようになる。」初めて知った時、衝撃だった。物、人、場所、数、色を意識して指示をつくる。乱発しては効果がなくなる。ここぞという時に使う。難しいけど、取り入れていきたい。2013/04/19
にくきゅー
3
久しぶりに読んだ。以前読んだときは、AさせたいならBと言えは間接性の原理に支えられているなぁと思ったが、今回は知的に子どもを動かす、という大前提の部分が印象に残った。子どもに言うことをきかせるための方法とかではないのだよなぁ。本質を取り落とさないようにしたい。2019/02/23