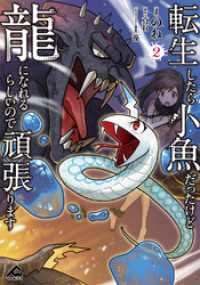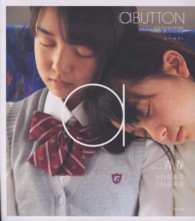内容説明
スピーチのマンネリ化、話す子の偏り、人の話を聞けない―そんな症状が学級に現れた時、「おーい!」クイズをしよう、写し絵ゲームをしよう、早口言葉作りをしよう、という実践を取り入れていくと、指名なし発言やミニ対話、ディベートで主張が出来るようになる。ウチの学級の子?耳を疑うような大変身を遂げる指導のツボ。
目次
1 こんな場面にこの手だて(一年のスタート、授業開きの注意点は―「多様性」が生まれる教材を授業開きで!;朝のスピーチがマンネリ化したとき―デジカメスピーチで変わる朝のスピーチ ほか)
2 こんな子どもにこの手だて(言いたいことだけを言って、人の話を受け入れない子ども―「うなずき力と質問力」アップでだれでも安心して話せる!;話しを深められない子ども―生の声を教材に、深まり合う話し合いへ ほか)
3 こんな力を高めたい!日常活動(全学年・はりのある声で生き生きと語らせたい!―詩の暗唱指導で声づくり;全学年・すべての子どもに話す機会を与えたい!―全員がスピーチ「朝の輝く一言!」 ほか)
4 こんな力を高めたい!一時間の授業(低学年・声を出す楽しさを感じさせたい!―「おーい!」クイズを使って、だれでも声が出せる学級に!;中学年・説明する力・質問する力を高めたい!―写し絵ゲームで説明力・質問力アップ! ほか)
5 こんな力を高めたい!一単元の授業(低学年・声を出す楽しさを味わわせたい!―「ここ(心)から(体)」から始める音読授業
中学年・相手の話を踏まえて質問したりコメントを言ったりする力をつけたい!―「鉛筆対談」「モデルビデオ」で、インタビューのポイントをつかませよう ほか)
著者等紹介
岩崎直哉[イワサキナオヤ]
1979年神奈川県横浜市に生まれる。東京学芸大学教育学部卒業。新潟市立新津第一小学校、佐渡市立小村小学校を経て、現在、五泉市立五泉南小学校勤務。基幹学力研究会幹事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。