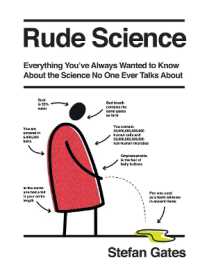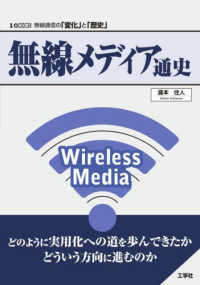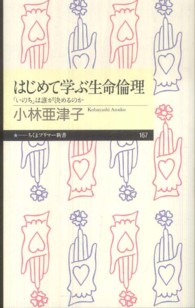出版社内容情報
教職は創造的な仕事です。子どもの学びに携わる教師が自分の仕事を愉しみ、にこにこわくわくしてこそ学校ではないでしょうか。そういう環境の中で子どもは学ぶことの楽しさや喜び、働くことの愉しみを感じ取るものです。今こそ伝えたい、「教師の魅力」「授業の魅力」。
目次
第1章 子どもとのかかわりを愉しむ
第2章 授業づくりを愉しむ―国語編
第3章 教材研究を愉しむ―国語編
第4章 授業づくりを愉しむ―道徳編
第5章 教材開発を愉しむ―道徳編
第6章 教職を愉しむ
著者等紹介
堀裕嗣[ホリヒロツグ]
1966年北海道生まれ。北海道教育大学札幌校・岩見沢校修士課程国語教育専修修了。1991年札幌市中学校教師として採用。1992年「研究集団ことのは」設立
宇野弘恵[ウノヒロエ]
1969年北海道生まれ。旭川市内小学校教諭。2000年頃より、民間教育サークル等の学習会に参加、登壇を重ねている。思想信条にとらわれず、今日的課題や現場に必要なこと、教師人生を豊かにすることを学んできた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- ヒールを脱がせて ~完璧主義が激甘後輩…
-

- 洋書電子書籍
- テロリズムとの闘い:ニクソンからオバマ…