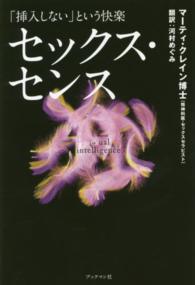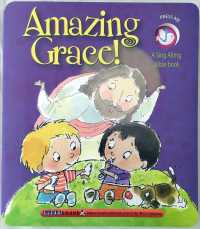内容説明
本書での提案は、これまでの作文指導の在り方を見つめ直すところから始まった。学級という集団の場で行われている「書くこと」の活動があまりにも“個”に埋没し過ぎていたのではないか、という問題点を取り出している。双方向型作文学習を、教育現場において積極的に創り出していくために、具体的な実践事例を取り上げて、その手順や方法を提示した。
目次
1 「伝え合う力」を高める双方向型作文学習の提唱(「コミュニケーション」という用語の危うさ;「コミュニケーション」という用語に関わる歴史的背景 ほか)
2 双方向型作文学習の構想(「コミュニケーション作文」という用語の曖昧性;「コミュニケーション作文」における“双方向型”の作文学習事例 ほか)
3 従来型の作文学習を双方向型作文学習に変える(簡単な挿し絵をもとに友達同士で“お話”作り;お互いの思いを“手紙”に託す ほか)
4 双方向型作文学習の創造(「ラジオドラマのシナリオ」作りで双方向型作文学習;「連詩」作りで双方向型作文学習 ほか)
著者等紹介
大内善一[オオウチゼンイチ]
1947(昭和22)年、茨城県生まれ。東京学芸大学教育学部国語科卒業後、国公立の小学校、中学校教員などを経て、東京学芸大学大学院教育学研究科国語教育専修修了。秋田大学教育学部教授を経て、現在茨城大学教育学部教授。所属学部全国大学国語教育学会(理事)、日本教育技術学会(理事)、日本言語技術教育学会(理事)、全国教室デイベート連盟(理事)、日本読書学会、表現学会、他。著書に『戦後作文教育史研究』(1984年、教育出版センター)、『国語科教材分析の観点と方法』(1990年)、『発想転換による105時間作文指導の計画化』(1991年)、『「白いぼうし」の教材研究と全授業記録』編著『実践国語研究』別冊119号(1992年)、『戦後作文・生活綴り方教育論争』(1993年)、『国語教育基本論文集成』共編著 第8巻・第9巻(1994年)、『思想を鍛える作文授業づくり』(1994年)以上明治図書、『「見たこと作文」の徹底研究』(1994年、学事出版)、『戦後国語教育実践記録集成〔東北編〕』全16巻共編著(1995年、明治図書)、『書き足し・書き替え作文の授業づくり』編著『実践国語研究』別冊156号(1996年、明治図書)『作文授業づくりの到達点と課題』(1996年、東京書籍)、『新しい作文授業・コピー作文がおもしろい』(1997年、学事出版)、『コピー作文の授業づくり―新題材38の開発』編著『実践国語研究』別冊180号(1998年、明治図書)、他がある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。


![Plant Tribe: Vom glücklichen Leben mit Pflanzen : Das neue Buch der Urban Jungle Bloggers - [deutsche Ausgabe] (2020. 240 S. 250 Farbabb. 262 mm)](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)