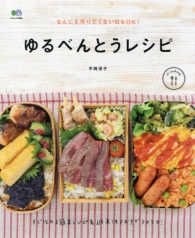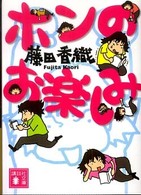内容説明
文芸教育研究協議会は、創立以来、読解力と表現力を育てることだけを目標とする国語教育のあり方を批判し、読解を超えて、人間そのもの、人間にとっての言語・文化やものごとの本質・法則・真実・価値・意味などをわかる力―認識力を育てることが国語科教育の目的であると主張してきた。そのために、「ものの見方・考え方」(認識の方法)を、発達段階に即して、系統的に指導することを試みてきた。『学習指導要領』が、言語事項を軸にして系統化を考えているのに対して、認識の方法を軸にして系統化を考えている。つまり、説明文教材も文芸教材も、作文・読書・言語・文法などの領域もすべて認識の方法を軸にして、互いに関連づけて指導するわけである。本書は、このような関連・系統指導の考え方に立って、どのような国語の授業を展開するか、二〇〇五年度版の新教科書の教材を取り上げ、解説した。
目次
低学年の国語でどんな力を育てるか(関連・系統指導でどんな力を育てるか;国語科で育てる力;本講座のテキストについて ほか)
一年の国語で何を教えるか(入門期の指導;「大きなかぶ」(ロシアのみんわ)
「じどう車くらべ」 ほか)
二年の国語で何を教えるか(「ふきのとう」(くどうなおこ)
「たんぽぽのちえ」(うえむらとしお)
ともこさんはどこかな ほか)
著者等紹介
西郷竹彦[サイゴウタケヒコ]
文芸学者・文芸教育研究協議会会長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。