出版社内容情報
見せかけだけの「主体的・対話的で深い学び」で子どもに力がつかない…そんな現状をどう打破するか? 本書は対話の能力や技術を高めるとともに、子ども達の人間関係も醸成する、ALを機能させる学びの在り方を解説します。個別最適な学びが求められる今、必読の一冊!
内容説明
「答えのない課題に臨機応変に対応する力」「人間関係を構築し調整していく力」を身につける!AL授業の成功法則110。
目次
第1章 AL授業10の原理(オーナーシップの原理;ネガティヴィティの原理;タスク・マネジメントの原理;リストアップの原理;コーディネイトの原理 ほか)
第2章 AL授業100の原則(ALの目的;ALの構成;ALの課題;ALの技術/インストラクション;ALの技術/グループワーク ほか)
著者等紹介
堀裕嗣[ホリヒロツグ]
1966年北海道湧別町生まれ。北海道教育大学札幌校・岩見沢校修士課程国語教育専修修了。1991年札幌市中学校教員として採用。1992年「研究集団ことのは」設立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
U-Tchallenge
3
堀裕嗣先生の著書はほとんどに目を通している。今回のテーマとなっているAL授業については過去の著作でも触れられている。それらがまとめられている内容となっている。しかし、ここまでまとまったAL授業論は他に見られないものだろう。これからAL授業について論じるならば必読の一冊に間違いないだろう。そして、現場でAL授業を実践していくならば、堀先生が提案されているAL授業の目的を考える必要があるだろう。AL授業について整理された視点を自身の授業にどう組み込んでいくかを考えていきたい。2023/02/11
しんえい
2
今年度から中学生を担当しているが、高校生への指導以上にALの重要性が高まったと感じたため読んだ。これは、現代の教師は全員読んだ方が良い……! 概念的な話だけでなく、具体的な指導言まで書かれている。以下、あとがきより引用。「人の他者意識は確かに、「私の中の他者」を超えない。しかし、第三者が「私の中の他者」を広げてくれることは大いにあり得る。(中略)たぶん「AL」とはそういう営みなのだと思う。」2023/05/21
ジーフー
2
日々何となく授業をしているだけではいつまでたっても変わらない。こういう書籍を書くことが最大のリフレクションなんだろうなぁ。自分が感じていた曖昧なことが明確に整理されて言語化され、自分の捉えがまだまだ浅はかだったことを思い知らされた。2023/03/12
-
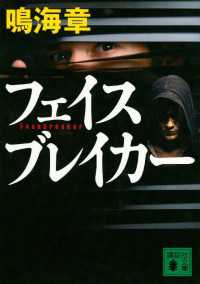
- 電子書籍
- フェイスブレイカー 講談社文庫







