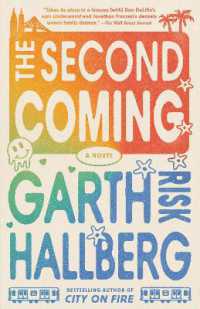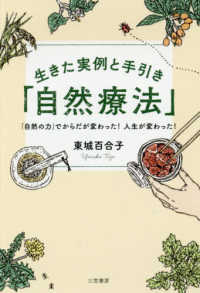出版社内容情報
「学級目標は教師が決める?子どもが決める?」「教師の机は前?後ろ?」「学級通信は出す?出さない?」…教師が行き当たる正解がわからない「モヤモヤ」の数々について、「Aがいい」「Bがいい」両視点の整理から「では、どうする?」まで、とことん考え抜ける1冊。
内容説明
コレって結局、どうしたらいいの!?正解なんてない?だったら全部考えて自分なりの「正解」を見つけだそう。学級目標は…教師が決める?子どもが決める?休み時間は…子どもと遊ぶ?子どもと遊ばない?教師の机は…教室の前に置く?教室の後ろに置く?
目次
学級システム
環境づくり
生活指導
学習指導
学習指導(教科)
その他の指導
保護者対応
著者等紹介
八神進祐[ヤガミシンスケ]
公立小学校教諭。1988年愛知県生まれ。愛知教育大学卒業。教育サークルMOVE代表。子どもたちの“ありのまま”を大切にした教育実践に取り組んでいる。教育論文入賞多数。第5回・第7回「全国授業の鉄人コンクール」優秀賞、フォレスタネット主催フォレワンGP初代MVP。YouTubeでは小学館「みんなの教育技術」より、授業力アップ動画を、Twitterでは「だいじょーぶ先生」としてアイデア溢れる教育実践を発信中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かるろ
2
これまでそうだったからとか先輩がやってたからと無思考でやっていた学級経営も解像度を上げて考える必要があると感じた。大事なのは指導者の意思とか意図とか狙いとか。提出物のチェックや給食指導、学び合いなど二項対立になっているテーマはたくさんあるんだけど、教師自身が哲学をもって決めていくことの大切さを暗示しているんだと思った。2025/01/02
かるろ
2
多くのテーマが教師として働く上で誰もが迷うような二項対立な話題だった。漢字テストのあり方や提出物の管理の仕方などがテーマだったが、両極論を述べる→折衷案みたいな流れだった。経験が浅い先生にはよい本なのかもしれない。2024/04/18