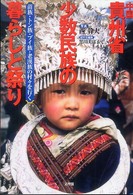内容説明
卒業後の就職で困らない為には、学校で何を学んだらよいのでしょうか。特別支援学級の子どもが通常学級の子どもと学びつながる意味とは。子どもの将来を見据えて、今出来ることがあります。
目次
第1章 保護者・雇用者の「本音」とは?(保護者の嘆き―保護者の視点から;「事業所が求める人材」とは?―採用側(人事担当)・就労支援者の視点から
マッチングのために出来ること)
第2章 子どもの進路の仕組み―雇用の仕組みと就労支援(子どもの進路―雇用の仕組みから;就労継続支援―よい事業所を探す手がかり;就職出来ないとき―卒業後もつながりを持ち続ける学校に ほか)
第3章 義務教育で出来ること(本当にそれが必要ですか?;仲間が必要―義務教育の中で多様な友人を;どんな授業をしたらよいのか ほか)
附章 特別支援担当教師からの視点―「つながり」を親亡き後の人生を生き抜く力として
著者等紹介
西川純[ニシカワジュン]
1959年東京生まれ。筑波大学生物学類卒業、同大学院(理科教育学)修了。博士(学校教育学)。臨床教科教育学会会長。上越教育大学教職大学院教授。『学び合い』(二重括弧の学び合い)を提唱。著書、編著書多数
深山智美[フカヤマトモミ]
1965年長崎県生まれ。長崎県小学校教員。2015年より2年間、内地留学。上越教育大学大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻、西川研究室にて『学び合い』における特別支援教育を学ぶ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みるこ
1
実践的でとても為になった。大切なのは九九を覚えることではなく、自分の得意なこと、苦手なことを理解し、説明できるようになること。コミュニケーションをとれること。愛されキャラになること。心に留め置こう。西川先生の講演会に行きたい。2020/10/01
小林だいすけ
0
事業所や企業、保護者などにインタビューして、学校でどんなことを学んで欲しいのかを探る。 この手法は通常級でも必要な考え方だと思います。 去年保護者に「あなたの職場で採用するならどんな人?」「その力はどうやって身につければよいと思いますか?」とアンケートを取ったことを思い出します。 そこにはやはり「向上心」とか「納期意識」といった言葉が書かれていました。2017/09/18


![Stories From Greek History; Tr. [By Sir A.J.E. Cockburn]](../images/goods/../parts/goods-list/no-phooto.jpg)