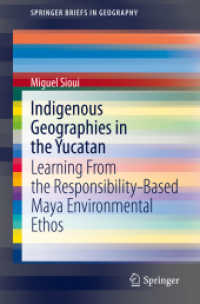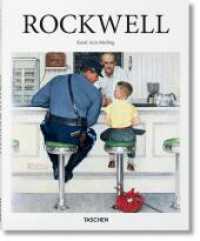内容説明
「材料七分に腕三分」という言葉が、料理の世界にあるという。これは、教育の世界でもいえることである。材料、つまり、教材の良し悪しが授業に大きく影響する。子どもの実態にマッチしたおもしろい教材を発掘できたとき、授業は成功したも同然である。わたしは、これまでに多くの教材を発掘し、開発してきた。その都度、いろいろな方法を使って開発してきたが、その中から有効だと思われるものを明らかにしたいと願った。つまり、「教材開発をするには、こんな考え方と方法でやれば、誰でもできる」という基礎的な技術を明らかにしたいと考えたのである。
目次
1章 教材開発に必要な基礎技術(逆思考の訓練をせよ―思考のパターン化を防ぐために;常に複数のテーマを追究せよ―怠け者にならないために;現地主義をつらぬけ―禁断の木の実を食べるために;本や新聞の読み方を工夫せよ―正確な情報をたくさん入手するために;一人の子どもを思い浮かべよ―一人ひとりの子どもを伸ばすために;見る目とセンスをみがけ―一つのものが多様に見える目をもつために;すべてのものを「師」にせよ―幅広い見方考え方を身につけるために)
2章 教材開発のノウハウ(子どもを熱中させる「ネタ」研究―授業研究に欠けているもの;授業に生きるネタ開発のポイント―子どもが追究するネタをさぐる;子どもの中の教材を創りかえる―子どものくらしの中からネタを発掘する;地理学習・こんな教材が子どもの目を開く―社会に目を開く教材には発展性がある;時代順の歴史学習を疑う―歴史教材の見方が変わる;ニュースをネタにしあげる―新しい社会の動きを見る目を養うために)
3章 子どもが熱中する教材の発掘例(教材をクイズにまとめる―クイズ形式で意欲化をはかる)
4章 こんな素材をネタにしたい
著者等紹介
有田和正[アリタカズマサ]
1935年福岡県生まれ。玉川大学文学部教育学科卒業。福岡県の公立校、福岡教育大学附属小倉小学校、筑波大学附属小学校を経て愛知教育大学教授。1976年より社会科・生活科教科書(教育出版)の著者。1999年3月愛知教育大学定年退官後、教材・授業開発研究所代表、東北福祉大学特任教授を歴任。2014年5月没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
pinkie
かんとっくま
桜井和寿