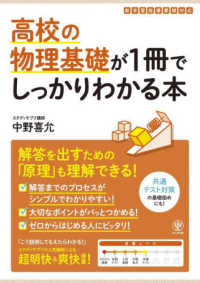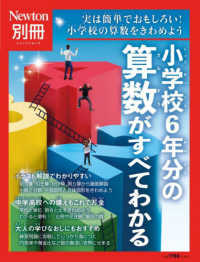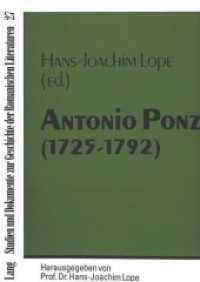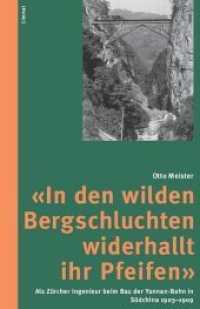目次
第1章 子どもを自立へ導く学級経営ピラミッド(公教育が終わったときに、どんな人に育っていればよいですか;自立に必要な3つの資質 ほか)
第2章 規範意識を育てる(自由でのびのびとした雰囲気をつくる;規律を浸透させ秩序をつくる ほか)
第3章 共に生きる姿勢を育てる(子ども達と目指す姿を共有する;学級集団の関係づくり強化への道筋 ほか)
第4章 目標をもって努力を続ける姿勢を育てる(成功体験を保障する;やればできる事実を創る ほか)
第5章 個人の自立と集団の自治を促す(精神的な自立を促す;リーダー体験を通して、よりよい集団をつくる力を育てよう ほか)
著者等紹介
大前暁政[オオマエアキマサ]
岡山大学大学院教育学研究科(理科教育)修了後、公立小学校教諭を経て、2013年4月より京都文教大学准教授に就任。複数の大学の教員養成課程において、教育方法学や理科教育学などの教職科目を担当。「どの子も可能性をもっており、その可能性を引き出し伸ばすことが教師の仕事」ととらえ、現場と連携し新しい教育を生み出す研究を行っている。文部科学省委託体力アッププロジェクト委員、教育委員会要請の理科教育課程編成委員などを歴任。理科の授業研究が認められ「ソニー子ども科学教育プログラム」に入賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
き
25
子どもを自立へ導くには、「規範意識を育て、自己肯定感を高め、他者と共に生きる喜びを味わわせながら、目標に向かって努力を惜しまない子を育てていく」学級経営をすればよいと筆者は表現している。その前提として、「子どもを自立に導くための学級経営の理論を、教師が知っている」必要がある。今の自分の実践を振り返り、学級をどう高めていくか考えるきっかけになった。2021/01/16
TWIST
5
学級経営に必要な知識や技能をすべてが詰まっている。具体例が多いので、学級のイメージもわく。 いやー、すごいです。 学級経営を語るなら、絶対に読まないといけない本。2020/06/17
onoeume
5
この本が学級経営の原典とも言えるものです。全員内容を知らないとまずいです。2022/01/22
風光明媚
5
学級経営に関するすべての内容を網羅したすばらしい書籍です。内容が実践的で、具体的なので、教室での指導がイメージできます。 昔から「集団づくり」の指導が大切だと学級経営では考えられてきました。「集団づくり」の系統性と内容をわかりやすく解説してくれています。先哲の実践を踏まえているのも、他の本にはない魅力です。さらに、学級経営の構造をピラミッド型で示し、授業づくりとの連動を解説してくれています。著者の学級経営がどのような理論によって行われてきたのかが、その背景がつかめました。目次だけでも意識改革になります。2022/02/11
楽しく生きる
4
学級経営のゴールがわかりました! 教師なら学級経営のゴールとやり方を両方知っておかないといけないと思いました。 ピラミッド型の構造図がわかりやすく、「ああ、こういう段階に今いるのだな」と、客観的に判断できるようになります。 4月の学級の状態からどこまで高められるのか? その判断基準が学べます。 教師なら、学級の状態を判定できる「目」をもっていないといけないなと、焦りました!!2022/02/18