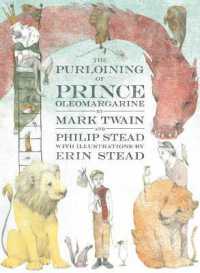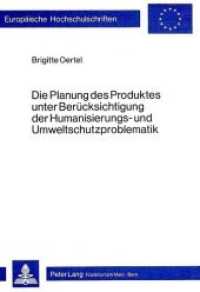目次
第1章 「安心感」不足が荒れを引き起こす(クラスの荒れのきっかけは子どもからのSOS;不安定になることで安定を保っている ほか)
第2章 「安心感」の無さが不登校を生む(不登校は「もう限界です」というサイン;我慢した時間だけ不登校になる ほか)
第3章 「安心感」を生むクラスづくりのポイント(「見守られている」と思える状態をつくる;「発言してもいいんだ」と思える状態をつくる ほか)
第4章 「安心感」を生む子ども対応のポイント(人の話を聞こうとしない子への対応;友だちをすぐ叩く子への対応 ほか)
第5章 子どもたちの「サポーター」としてできること(「子ども」を早く「大人」にしてはいけない;子どもの「つぶやき」にこそ本音がある ほか)
著者等紹介
城ヶ崎滋雄[ジョウガサキシゲオ]
1957年、鹿児島県生まれ。大学を卒業後、千葉県公立小学校教諭となる。20歳代では、教育委員会に出向し、社会教育に携わる。30歳代では、不登校対策教員として不登校についての研鑽を積む。40歳代では、荒れたクラスの立て直しに努める。50歳代では、子育て経験をいかして家庭教育にも活動を広げ、学級担任として現在も教壇に立つ。連載が10年目をむかえた教育情報誌『OF(オフ)』(新学社)や子育て情報誌『Popy f(ポピーエフ)』(新学社)を通して、若い先生や保護者にアドバイス・情報発信をおこなっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
jotadanobu
0
子どもを大人扱いせず、子どもらしく扱うと書いてあったが、印象として城ヶ崎先生は、「一人ひとりを」「一人の人間として」扱っているという印象だった。当たり前のことに思えるが、日々指導者として立っていると忘れてしまうことがあることだ。 「待つ」というのもすごいレベルで、個に応じてありとあらゆる手で事あるごとに働きかけ、そしてそれを、続けながらひたすら「成長を待つ」といった感じだ。 教師はどれだけ根気強く「待ち」続けなければならない仕事がとここ最近思うが、それでもその先にある一瞬の、一歩の成長が楽しみで、嬉しくて2015/08/14
-

- 和書
- ウェブスター 辞書の意味