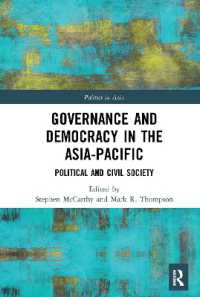目次
第1章 生徒が苦手な教材―楽しい授業に大転換する10の原則(数を示して、教えることを限定する;練習量を確保する ほか)
第2章 生徒が苦手な教材―楽しい授業に大転換する指導アイデア(文法教材;古文教材 ほか)
第3章 生徒が苦手な「書く」活動―楽しい授業に大転換する指導アイデア(一文を短くするのが苦手;常体と敬体の統一が苦手 ほか)
第4章 生徒が苦手な「話す・聞く」活動―楽しい授業に大転換する指導アイデア(スピーチ教材;聞き取り教材)
第5章 生徒が苦手な「書写」―楽しい授業に大転換する指導アイデア(用具の扱いが苦手;筆遣いが苦手 ほか)
著者等紹介
松原大介[マツバラダイスケ]
1960年京都市生まれ。1983年國學院大学文学部卒業。1994年新潟県岩室村立岩室中学校教諭。2001年新潟県聖篭町立聖篭中学校教諭。2008年新潟市立宮浦中学校教諭。2015年新潟市立新津第一中学校教諭。TOSS中学新潟いなほの会教育サークル日本海(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
虎哲
1
過度な一般化が目立つ。発問が収束的思考を促すに留まっている。教科書を上手に教えることを望む人にとっては良いが、知識を効率的に習得させること自体にどんな意味があるか考えさせられた。知識の定着についてもこれで良いのかというところもある。簡単に手に入れた知識はすぐに抜けていくと考えているからだ。また要約の指導については正直本当にこれで良いのかと思った。中学校国語科について知識の習得だけでなく、概念や思考と結びつけたいと考えているので内容に物足りなさを感じた。私は著者や出版社の想定する読者に合わなかったのだろう。2018/11/08
にくきゅー
0
堅実な授業だと思う。パーツによる授業構成で漢字、視写、聴写をすることで基礎的な学力の保障をしている。また、説明をできるだけ削減し、発問と作業で知識的な内容を授業している。演習量も豊富なため、知識の定着もされるであろう。この一斉指導の実例からALに取り入れることはなにか、考えねば。2017/08/19
どこかの国語教師
0
2016年17冊目。TOSSの実践を、具体例を挙げながら体系的にまとめた感じ。参考になる箇所は多いし、確かに国語の基礎的な力は付きそうに思う。が、あまりにもテクニックに偏りすぎているのではないか。基本、一問一答の授業スタイル。表面上はできるようになっていくだろうが、本当に考えるというところに至るのか。知ること.・考えることの喜びが、置き去りにされそうな気がする。2016/03/22