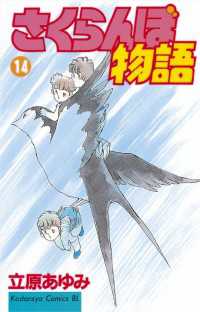内容説明
日本一ハッピーな教室をつくる秘訣とは?子どもを温め、気付かせる。主体性と協働力を伸ばす、共感と言葉がけを。教室や授業で子どもとつながり、伸ばす極意。子どもは皆、素晴らしい力をもっています。一人ひとりの力が発揮され、個性が磨かれるためには、教師の子どもの見方と共感が何より重要なのです。
目次
第1章 ハッピー教育入門(僕が考えるハッピー教育;こんな子どもを育てたい ほか)
第2章 子どもと向き合う時に大切にしていること(いろんな目線で捉えてみる;よしあしの中を流れて清水かな ほか)
第3章 子どもが成長するように(困らな感を困り感に;困り感から自立に向けて ほか)
第4章 子どもと子どもがつながる(子どもが授業でつながるためのスキル指導;今と昔は違う ほか)
第5章 自分を磨き続ける(磨くという言葉から(両親のおかげで生きている)
人様との出会いのおかげで今がある ほか)
著者等紹介
金大竜[キムテリョン]
1980年生まれ。日本一ハッピーな学校をつくることを夢見る、教師歴14年目の大阪市小学校教員。周囲からは“ハッピー先生”と呼ばれている。教育サークル「教育会」代表。「明日の教室」をはじめ、各地のセミナーで講師を務める。また、「あいさつ自動販売機」など、学級づくりにかかわる取り組みが、様々なメディアに取り上げられている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
jotadanobu
2
様々な手法に手を伸ばしては実践、課題にぶち当たってはまた別の手法へ、、、そんな3年間を過ごし、ここ最近どうにもならない行き詰まり感を感じていた。いつの間にか表面しかすくっていなかった。学びが広がっていくように見えて周りが見えなくなっていった。でも、ここ最近の本との出会い、人との出会いにより、感じ方や考え方が変わりつつあるのを感じる。枝葉は自分と目の前の子どもたちでいくらでも創り出せる。大切なのはこの世界と関わる自分にしか創り出せない軸。たくさんの人の軸に触れて、つくっていきたい。そんなこと強く感じている。2016/01/24
BECCHI
1
楽しみながら努力をして学び、大事なことをきちんと掴んだ上で、教育しているんだなぁと思いました。でも、自分が最近気づくことができていたことと近いものがあり、嬉しくも思った。「温める」という指導では、男女で40秒以内で手を繋ぐアクティビティは、自分のクラスでも使わせてもらった。伝えたいことは体験を通すべきだなと感じた。これは大きな発見であった。この本は、金先生の学級経営がよーくわかる本になっている。ヒントがたくさんあり、本当に勉強になった!同い年だが金先生との差は激しい。子どもたちのためにも、もっと学びたい。2016/02/19
mori
1
金先生は、考え方が広くしなやか。中庸、いい言葉だな。子どもに対するあたたかさが現れた本。目の前の子どもを見ながらの実践や言葉かけは説得力あり。子どもに言うことを自身はできているかを問い、ご自身もチャレンジされている。自分が本当によいと思うことしか伝わらないのだと思う。2016/02/07
jotadanobu
0
幅広くいろいろな物に触れながら考えながら、やがては自分の軸を見つけていく。もうすでに自分には全てのものが詰まっている。あとはそれを、どう育てていくか。2016/10/08
はまちゃん
0
子どもがハッピーになるための働きかけやその環境をつくるための秘訣とは? 小学校教師の著書が語るハッピー教育。 子どもの困り感に気づく、子どもの名前から保護者がどんな願いを持っているか?を考えるなどの教育方法も魅力的だったが、それ以上に著者の教育哲学が心に響いた。 教育ってその方法とか、誰がやっているとかに目が行きがちだけど、その教育の目指すところや本質を知ることがとても大事だなと気づかせてくれた1冊。 困ったとき、何度も読み返したい。


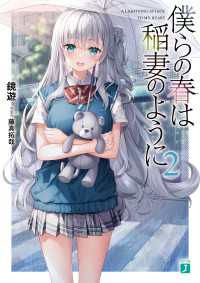

![[1話売り]去勢転生 第1話 後編 ヤングアニマルコミックス](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0791920.jpg)