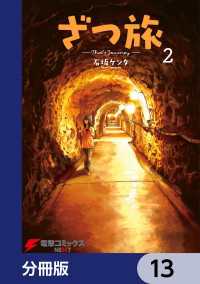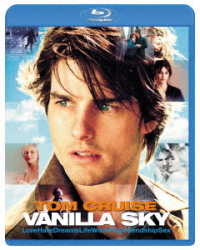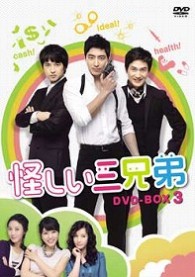- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教育問題
- > いじめ・非行・不登校・引きこもり
内容説明
本書では、40のいじめ対応での困った場面を想定し、なぜそうなのか。どうしたらよいのか。という視点で考えています。また実際の会話例を良い例、悪い例で示しています。
目次
Introduction 生徒が教師に困っている場面(「悪気がないから気にするな」と言われる場合;話をきちんと聞いてもらえない場合 ほか)
1 いじめ被害者への対応で困った場面(いじめの事実がはっきりしているのに、被害者が認めない場合;いじめをされていることに気が付かない場合 ほか)
2 いじめ加害者への対応で困った場面(いじめが悪いことだと思っていない場合;いじめの事実を加害者が認めない場合 ほか)
3 いじめ傍観者への対応で困った場面(いじめの事実を知らせてこなかった場合;見ているだけだから悪くないと思っている場合 ほか)
4 いじめ保護者への対応で困った場面(加害者の保護者が指導内容に抗議してきた場合;加害者の保護者が「むしろ被害者だ」と訴えてきた場合 ほか)
著者等紹介
千葉孝司[チバコウジ]
1970年、北海道生まれ。公立中学校教諭。ピンクシャツデーとかち発起人代表。いじめ防止や不登校に関する啓発活動に取り組み、カナダ発のいじめ防止運動ピンクシャツデーの普及にも努めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あべし
2
いじめに限らず、子どもとのやりとりで大切な「聞く」技術を学ぶことができた。 よくない例として挙げられていたやり取りは、教師が「決めてかかっている」というところ。頭ではもう決まっていることでも、決めてかかられたら、相手はもう心を閉ざしてしまう。だから、どんな場合でも、聞いて、相手の口から話させることが大切だと思った。トレーニングは必要だと思う。 共感するために、相手の言葉を繰り返すこと。相手の気持ちを聞くこと。しかし、教師としての考え方や価値観、その時どう見えたかは遠慮なく伝えること。決定権は子どもに。2023/08/05