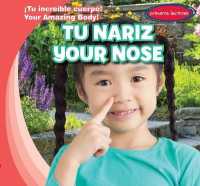内容説明
厳しい就職事情の中で、生涯の幸せを紡ぐには?特別支援学級の子どものリアルな就職事情と、就労の仕組み。「今、卒業後の幸せのために出来る」準備と取り組み。
目次
第1章 厳しい就職までの状況(入学式から始まっている;特別支援の子どもの進路;「就学」のスタートライン;「就労」へのスタートライン)
第2章 就労の仕組み(企業の就労を希望する場合;福祉の就労を希望する場合;ちょっと待って)
第3章 マッチングの仕方(意識を持つこと;思い込みは怖い;マッチング)
第4章 生活が変わる(今までの生活;その時のために、出来ること;グループホームから親なきあとまで)
第5章 学校卒業後の幸せ(幸せな就職;生活介護施設での幸せ;障害がとても重い子どもの幸せ)
著者等紹介
西川純[ニシカワジュン]
1959年東京生まれ。筑波大学生物学類卒業、同大学院(理科教育学)修了。博士(学校教育学)。臨床教科教育学会会長。上越教育大学教職大学院教授。『学び合い』(二重括弧の学び合い)を提唱。著書、編著書多数
深山智美[フカヤマトモミ]
1965年長崎県生まれ。長崎県小学校教員。2015年より2年間、内地留学。上越教育大学大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻、西川研究室にて『学び合い』における特別支援教育を学ぶ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小林だいすけ
0
特別支援教育を受ける子どもたちの未来を考えることは、ひいては社会全体のことを考えることだと思います。 また、社会全体を考えながら教育に携わることは必須だとも思います。 どうしても、現場では学校と社会が分断され、「学校社会」が作られてしまいがち。 その中で適応する(させられる)子どもたちが、社会に出た時にミスマッチを起こす。また、社会そのものが不具合を是正できずにいる。 そんな連鎖に歯止めをかけようと頑張っているのが『学び合い』の仲間たちなんじゃないかと思います。2017/10/25
pocky
0
将来をイメージした時に何が必要な力か。早いうちから考えておくことが大切。最終的にはコミュニケーション。本人たちが必要な力を考えると同時に,やっぱり周囲の理解や受容が進むことが不可欠だと感じる。2019/06/16