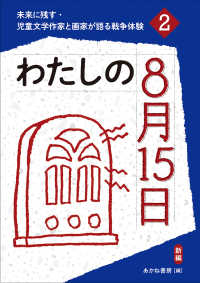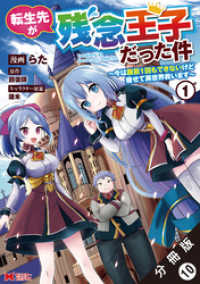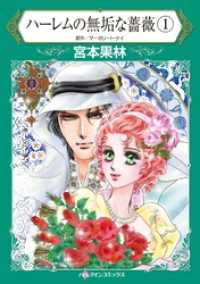目次
1章 クラスがまとまる!うまくいく!知っておきたい「ヒドゥンカリキュラム」(「ヒドゥンカリキュラム」とは何か;ヒドゥンカリキュラムが教育を決定づける;自分の個性に合わせたヒドゥンカリキュラムをつくろう ほか)
2章 トラブルを防ぐ!対応する!目的別・実例でわかるヒドゥンカリキュラム(学級経営 学級がなんだかぎすぎすしている―学級にプラスの風を送るヒドゥンカリキュラム10;個別対応 学級に気になる子どもがいる―気になるあの子を包み込むヒドゥンカリキュラム10;授業づくり 聴くことに集中できない―聴く子どもが増えるヒドゥンカリキュラム10 ほか)
3章 ヒドゥンカリキュラムを使いこなすには(若いうちに身に付けたい仕事観;若手だからこそできること、できないこと;困ったときは、どうしたらいいの? ほか)
著者等紹介
多賀一郎[タガイチロウ]
神戸大学附属住吉小学校を経て私立小学校に長年勤務。現在、追手門学院小学校講師。専門は国語教育。神戸で親塾を開講して、保護者教育に力を注いでいる。また、教師塾やセミナー等で、教師が育つ手助けをしている。絵本を通して心を育てることもライフワークとして、各地で絵本を読む活動もしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。