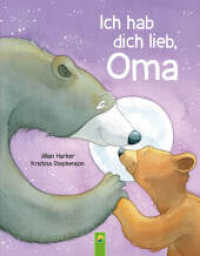出版社内容情報
江戸時代の武士は一枚岩ではない。史料を渉猟し、身分格差、結婚、相続など、藩に仕える武士の内実に迫る『武士の家計簿』の姉妹編。
磯田史学の真髄にして、ベストセラー『武士の家計簿』の姉妹編。江戸時代の武士は一枚岩ではない。侍・徒士・足軽以下の三層構造になっていた。史料を渉猟し、身分内格差、禄高、結婚、養子縁組、相続など、藩に仕える武士の内実に迫る。
内容説明
全国を行脚し集めた厖大な史料を社会経済史的に分析し、儀礼、禄高、婚姻、養子縁組、相続などの実態から江戸時代の藩に仕える武士の実像に迫る。武士は侍、徒士、足軽以下の三層から構成され、あらゆる面で明確な身分内格差があったことが鮮やかに浮かび上がる画期的論考。
目次
第1部 家格と階層秩序(格と礼の秩序;格式禄高と婚姻;格式禄高と養子;婚姻・出生の階層差)
第2部 階層の再生産構造(徒士層の編成制度;足軽の編成制度;士・徒士・奉公人の相続実態;「譜代」足軽の編成実態)
第3部 居住形態と経済構造(足軽・中間の供給構造;侍・徒士・足軽以下の存在形態;侍層と武家奉公人;終章)
著者等紹介
磯田道史[イソダミチフミ]
1970年、岡山県生まれ。2002年、慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(史学)。現在、静岡文化芸術大学准教授。史料を読みこみ、社会経済史的な知見を活かして、歴史上の人物の精神を再現する仕事をつづけている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
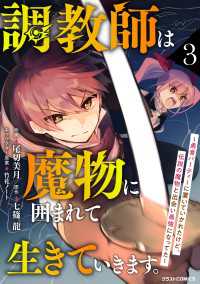
- 電子書籍
- 調教師は魔物に囲まれて生きていきます。…
-

- 和書
- 真田幸村 文春文庫