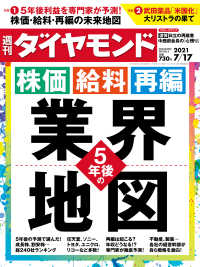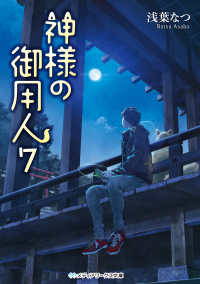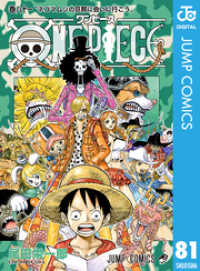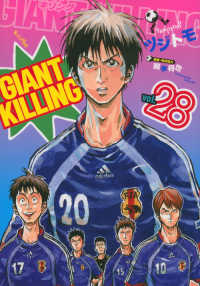出版社内容情報
失業対策、国債発行、保護貿易……デフレ脱却の提言を果敢に行った1930年代のケインズ。今日なお示唆に富む、諸論稿を初邦訳。
1930年代のケインズは、直面した経済的困難に対して、問題の本質を理論的に解明し、具体的で現実的な政策手段を提案した。そして、理論的著作の執筆だけでなく、新聞や雑誌への寄稿、あるいは講演という形で、より広範な市民に向けて、みずからの考えを噛み砕いて、積極的に提示し続けたのである。その優れた著作からだけでは掴めない、ケインズのもう一つの魅力と重要性は、ここにある。
デフレ大不況、財政問題、国際通貨問題、貿易問題など、ケインズが格闘した諸問題は、いずれも、今日のわれわれが直面している問題でもある。具体的に、ケインズは、?@雇用の創出効果は広範に及び、十分に大きいこと、?A財政への悪影響は、一般に考えられるよりも小さいこと、?B正常水準からの物価上昇は、景気回復に必ず伴うものであり、インフレではないこと、?C長期金利の上昇を招いて民間投資を締め出したり、国債の借換コストを上昇させたりはしないこと、などを主張した。まさにこれは、今日の脱デフレ政策と通底するものである。
そこで、本書は、「失業の経済分析」「世界恐慌と脱却の方途」「ルーズベルト大統領への公開書簡」「財政危機と国債発行」「自由貿易に関するノート」「国家的自給」「人口減少の経済的帰結」など、1930年代のケインズの重要論稿を十数本、精選し、「世界恐慌」「財政赤字と国債発行」「自由貿易か、保護貿易か」「経済社会の国家の介入」といったテーマ別に編集した。
本書に収録された、いずれも未邦訳の諸論稿は、ケインズの時代と共通する経済的問題に直面するわれわれにとって、多くの示唆や教訓を含み、今後の指針ともなりうるだろう。
内容説明
デフレ不況、失業、財政赤字、国債発行、自由貿易と保護貿易、為替レート、人口減少など、今日にも通じる諸問題に取り組み、市民に向けて平明な言葉で政策提言を行った一九三〇年代のケインズ。今日なお示唆に富み、ケインズ理論のエッセンスが分かる諸論稿を初邦訳。
目次
1 世界恐慌(経済不況のメカニックス;失業の経済分析 ほか)
2 財政赤字と国債発行(国債借換計画と長期金利;財政危機と国債発行 ほか)
3 自由貿易か、保護貿易か(自由貿易に関するノート;関税に対する賛否両論 ほか)
4 経済社会と国家の介入(国家計画;人口減少の経済的帰結)
著者等紹介
ケインズ,ジョン・メイナード[ケインズ,ジョンメイナード] [Keynes,John Maynard]
1883年‐1946年。20世紀前半を代表するイギリスの経済学者。名門のイートン校とケンブリッジのキングスカレッジで学ぶ。1919年、パリ講和会議に大蔵省首席代表として出席。帰国後、直ちに『平和の経済的帰結』(1919年)を刊行し、ヴェルサイユ条約を批判。その後、『貨幣改革論』(1923年)を経て、1930年、その革新性ゆえに論争を引き起こした『貨幣論』を発表。後に『説得論集』(1931年)に収録される論稿で各種の政策論争も展開
松川周二[マツカワシュウジ]
1948年北海道生まれ。立命館大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
燃えつきた棒
Francis
日の光と暁の藍
Moriya Masahiro
ハンギ