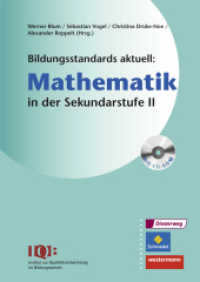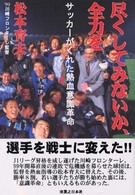出版社内容情報
【目次】
内容説明
物語を読み取れない子どもが増えている。葬儀で村人が煮炊きする場面を「死体を煮ている」と誤読する小学生たち。家庭による教育機会の格差を、公教育が是正できなくなっている―取材をすすめる中で著者は、現実に直面する。根源には何が?国語力は再生できるのか?現代日本の不都合な真実に正面から挑む、渾身のルポ。
目次
第一章 誰が殺されているのか―格差と国語力
第二章 学校が殺したのか―教育崩壊
第三章 ネットが悪いのか―SNS言語の侵略
第四章 三四万人の不登校児を救え―フリースクールでの再生
第五章 ゲーム世界から子供を奪還する―ネット依存からの脱却
第六章 非行少年の心に色彩を与える―少年院の言語回復プログラム
第七章 小学校はいかに子供を救うのか―国語力育成の最前線1
第八章 中学校はいかに子供を救うのか―国語力育成の最前線2
著者等紹介
石井光太[イシイコウタ]
1977年、東京都生まれ。ノンフィクション、小説、児童書などを幅広く手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shun
35
話題になった”「ごんぎつね」を読めない子供たち”というコラムが伝える国語力低下の懸念。最初はにわかに信じがたい状況に思えましたが次第に危機感を抱くようになった。小学生とはいえ、亡き母を鍋で煮ている光景ですと真面目に議論する子供たち。そこには読解力だけでなく想像力や感性といったものまで欠けている現状があった。その原因は家庭環境の他にも現代の複雑な社会、例えばSNSや学習指導要領に追加されたSDGsや多様性といった新しい概念まで様々だ。問題は根深く教育環境の改善が急がれる。一人でも多くの人に読んでほしい1冊。2025/07/23
くるぶしふくらはぎ
23
「国語力」格差が社会的環境格差を生む。一因として「徒弟制度の崩壊」が挙げられている。便利なアプリの登場で、バイトをする人は職場で育てらず、「使える人」だけが重宝され、「人」を根気よく育てる風土がないので「使えない人」はいつまで経っても何を直せばいいのか分からぬまま年齢を重ね、低賃金のまま。終章の「感情労働」にもつながる。理不尽な状況でも自分をコントロールする力は「国語力」がその土台となる。教育最前線の学校の取り組みに国語力UPの改善のヒントがあると提示されている。言葉は自分を作る根幹なんですね。2025/11/09
てくてく
10
「ごんぎつね」の葬儀シーンが理解できない子どもたちから始まって、コミュニケーションを下支えする国語力、言語化およびその理解力の欠如に由来するトラブルや問題、明確な理由が本人すらわからない不登校、ゲーム依存とそれによる言葉への影響など、様々な問題を取り上げた上で、国語力育成の最前線を紹介することで、国語力回復のために何が必要かを示唆する一冊。日本女子大附属中高の文庫本一冊を一学期間かけて精読する取り組みが魅力的だった。2025/07/12
チューリップ
8
国語力の低下。ごんぎつねについては、読解力というより経験不足という気もした。ただ、単語や乱暴な言葉での会話ですれ違う等、共感できる話も多い。もう少し、読み進めたい。2025/07/26
こぺたろう
7
実家で読了。元々、藤原正彦氏の「祖国とは国語」に感銘を受けたこともあって、国語をしっかり身に付けることが学問や社会生活の基礎になると考えてきました。子育てをする上でも国語の重要性を意識しています。本書で紹介されている事例は俄かに信じ難いですが、学校現場の先生方にも、国語力の低下を肌で感じている方がいるようです。これから学校教育のあり方がとうなっていくのか、以前より関心を持とうと思いました。2025/12/31