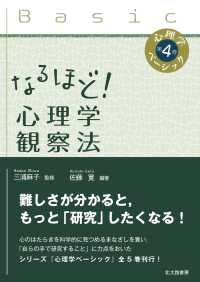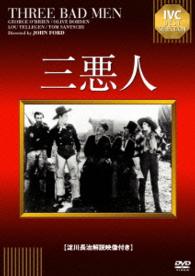内容説明
「絵師になりたき一念どうにも抑え難く」茨城県笠間を飛び出した15歳の山下りん。東京で工部美術学校に入学を果たし、西洋画の道を究めようと決意する。ロシヤ正教の宣教師ニコライに導かれ、明治13年、聖像画制作を学ぶため帝政ロシヤに渡るのだが―情熱に従って生きた日本初のイコン画家を描く圧巻長編。
著者等紹介
朝井まかて[アサイマカテ]
1959年大阪生まれ。甲南女子大学文学部卒業。2008年『実さえ花さえ』(のちに『花競べ』に改題)で小説現代長編新人賞奨励賞を受賞し作家デビュー。14年『恋歌』で直木賞、『阿蘭陀西鶴』で織田作之助賞、16年『眩(くらら)』で中山義秀文学賞、17年『福袋』で舟橋聖一文学賞、18年『雲上雲下』で中央公論文芸賞、『悪玉伝』で司馬遼太郎賞、19年に大阪文化賞、20年『グッドバイ』で親鸞賞、21年『類』で芸術選奨文部科学大臣賞をそれぞれ受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
のり
60
激動の明治に画家を志した「山下りん」。西洋画の道を究めようとするが、時代に阻まれる。画家仲間に紹介され、ロシア正教の「ニコライ」宣教師と運命の出会いで、新たな道が示された。聖像画師として腕を磨く為にロシアへ渡ったが…とにかく図太くないとやっていけない環境。言葉の壁も高い。帰国後も色々ありすぎた。教徒との信仰心の差。歳を重ねるにつれ、腑に落ちる事で景色が変わる。日露戦争も絡み、窮地にさらされる事も多々。それでも仲間も多かったし、波乱万丈だったが見事に生き抜いた。天晴。2024/08/30
kei302
46
超大作、参考資料の数もすごい。正教会と日本の関係を興味深く読んだ。信仰の心を持たずして聖画を描いていたことに思い至るまでの山下りんの長い道のり。聖歌は親しい存在だが、これまで絵にはあまり関心がなかったので、機会があればじっくり見たい。文庫解説は酒井順子さん「『好き』の先にあるものは」こちらも興味深く読んだ。2025/07/09
エドワード
44
常陸国笠間藩の下士の家に、絵が大好きな娘がいた。山下りん。自己主張の強いりんは、文明開化の世に、絵を学びに東京へ飛び出す。工部美術学校でイタリア人・ホンタネジーに洋画を学ぶが、彼の後任とあわず、ロシア正教会の画工となり、ロシア留学の機会を得る。しかし留学先の修道院で当たる大きな壁。「聖像画は芸術であってはなりません」ルネサンス風の絵画ではなくギリシャ風のイコン修行の日々だ。驚き、反発し、苦悩するりんの姿は、先進国へと走る日本の歩みに重なる。ずっと後で彼女は教えを理解し、日本随一の聖像画家となる。大作だ。2024/04/21
てつ
28
まかてさんの本は表現が柔らかく自然で美しい。日本人初のイコン画家山下りんの生涯を描く。何かに打ち込む表現者を描かせると天下一品。ロシア正教会に興味がなくとも、美術的素養がなくても没頭して読める名作です。2024/04/27
Y.yamabuki
23
日本初のイコン画家 山下りん。西洋画を追い求め、その切っ掛けとして始めたイコン画であったが、徐々に本来の聖像画師としての役割に目覚めていく。自らの生き方を貫いたりんの一生を興味深く読んだ。故郷に戻っての晩年は、革命後の女子修道院の人達の身を案じながらではあったが、慎ましくも穏やかな日々であったであろう。時折思い出すロシアと故郷笠間の美しい風景が心に沁みる。 2024/09/24