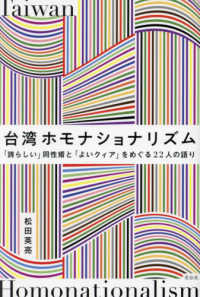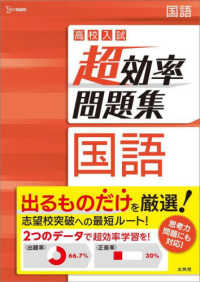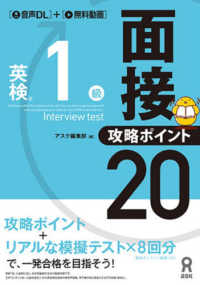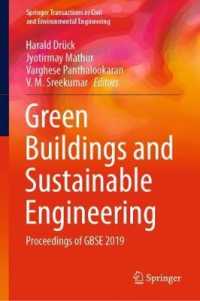内容説明
刺青の彫師が集まる台北の紋身街。食堂の息子・景健武は、彫師のケニーやニン姐さん、珍珠〓茶(タピオカミルクティー)屋の阿華など、一癖も二癖もある大人たちに囲まれ、街での暮らしを楽しんでいた。ある日、顔に刺青を入れたいとニン姐さんに依頼した女が現れて…(「黒い白猫」)。熱気溢れる雑多な街の人間模様を描く傑作連作集。
著者等紹介
東山彰良[ヒガシヤマアキラ]
1968年台湾生まれ。幼少期を台北で過ごした後、日本に移る。2003年、「このミステリーがすごい!」大賞銀賞・読者賞を受賞した『逃亡作法 TURD ON THE RUN』で作家デビュー。09年『路傍』で大藪春彦賞、15年『流』で直木賞、16年『罪の終わり』で中央公論文芸賞を受賞。17年に刊行した『僕が殺した人と僕を殺した人』では読売文学賞、渡辺淳一文学賞、織田作之助賞の3冠に輝く(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mike
76
以前台湾を旅行した時、漢字だらけの看板に"刺青"の文字がやたら目に付いた記憶がある。この小説は刺青店が立ち並ぶ台北の紋身街が舞台で食堂の息子が主人公。幼い彼の目を通して裏ぶれた街に住む大人の姿が描かれる。それは騒々しくて狡くて汚れていて身勝手で哀しい。なのに友だちからこの街を貶されると猛烈に腹が立つのだ。旅行者は知ることのない台湾の別の姿が東山さんのノスタルジックな筆致から見えてくる。西洋の翻訳本の様な読み心地だ。2025/10/13
sin
57
過去に寄り添って深く潜ってゆくと、どうやら自分は街を切り離して無頓着で人生を忘却に転落させているようだ。 だがしかし小説家は街と共に生きた自分を掘り起こし人生を物語に昇華させる。過去は過去でしかないと云う言い訳が自分の生き方なら、過去がただ過去に過ぎないのかと問い詰める姿勢が物語を紡ぐと云うことなのだろう。そうして自分の立ち位置を卑下してみて気づくのは、物語の中の物語の井の中の蛙が大海の鯨に問いかけた言葉の答えにあるだろう公平性だ。どんな場所に居ようと、どんな生き方をしようと人生は人生なのだから…。2023/06/03
エドワード
32
5年前に訪れた台北の街。表通りから一歩入ると、カオスな裏通りが広がる。刺青屋の集まる紋身街。台湾では気軽にファッションとして刺青を入れるらしいね?ビックリだ。エネルギッシュな、不思議な裏通り。大衆食堂の息子、小学3年生の景健武は、彫師のケニーやニン姐さん、探偵の孤独、チンピラの鮑魚、珍珠奶茶屋の阿華などの大人たちと暮らすこの町が好きだ。学校で作文「わたしの街」の宿題が出る。「紋身街なんて、ちっぽけな場所だろ、井の中の蛙じゃん。」と友人に言われた健武は、蛙を主人公にした作文を書く。これには泣かされたよ。2023/01/25
ヨノスケ
20
台湾の紋身街という地域が舞台の連作短編。主人公である少年の目線で猥雑な街とそこで暮らす人たちの様子が語られる。タトゥーの彫り師、タピオカ屋台店主、探偵、ヤクザ、娼婦など、自分は知らないはずの世界。でも不思議と、こみ上げるような懐かしい感情がわいた。少年が大人になる過程で身につけておきたい免疫がこの街には豊富に存在する。『将来の予期せぬ不幸に動じない方法を身をもって学べる街なんだな』と思った。2023/02/11
tomoka
16
東山さんの描く少年たちが好きです。場所や年代が違えど我が息子もこんな少年時代を過ごしていたのかなと思いながら読了。心地よい時間でした。2023/02/13