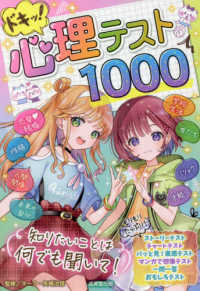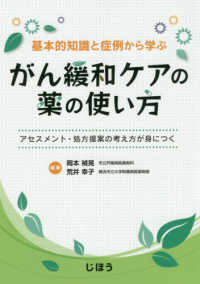出版社内容情報
何世紀にも亘り、その村の人達は本を籠一杯担ぎ、国中を売って歩く行商で生計を立ててきた――本を愛する全ての人に贈る、話題の書。
内容説明
トスカーナの山深いその村では、何世紀にもわたり本の行商で生計を立ててきた。籠いっぱいの本を担いで国じゅうを旅し、「読む」ということを広めた。―偶然の出会いに導かれ村人に消えゆく話を聞きながら、突き動かされたように書いた奇跡のノンフィクション。本と本屋の原点を描き、各紙誌で絶賛された読み継がれるべき1冊。
目次
それはヴェネツィアの古書店から始まった
海の神、山の神
ここはいったいどこなのだ
石の声
貧しさのおかげ
行け、我が想いへ
中世は輝いていたのか!
ゆっくり急げ
夏のない年
ナポレオンと文化の密売人
新世界に旧世界を伝えて
ヴェネチアの行商人たち
五人組が時代を開く
町と本と露天商賞と
ページに挟まれた物語
窓の向こうに
著者等紹介
内田洋子[ウチダヨウコ]
1959年兵庫県神戸市生まれ。東京外国語大学イタリア語学科卒。通信社ウーノアソシエイツ代表。欧州と日本間でマスメディアに向けて情報を配信。2011年、『ジーノの家 イタリア10景』で日本エッセイスト・クラブ賞、講談社エッセイ賞を同時受賞。2019年、ウンベルト・アニェッリ記念ジャーナリスト賞、2020年、イタリア版の本屋大賞・第68回露天商賞受賞式にて、外国人として初めて“金の籠賞(GERLA D’ORO)”を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ミカママ
519
永らく読みたいと思っていたこちら、なんとシアトルの古本屋さんにて遭遇。資源も満足な産業もない、あるのは周囲の膨大な栗の木と石ころだけ、という貧しい村モンテレッジョ。最初は石ころを背負って行商に出ていた村人が、商品に本を加えての旅に代わる。そこには文化を伝える、という彼らの誇りや使命もあったろう。現代と比べて想像もできないくらいの過酷な行脚、彼らの矜持をしかと読み取ることができた。電子全盛の世になれど、紙本を愛する読書家の気持ちは失くならない、と信じる。2024/05/12
KAZOO
112
イタリアの在住女性と言えばすぐ出てくるのが塩野さん、故人であられる須賀さん、内田さん、ヤマザキさんですね。この内田さんの本は単行本で読んでこの文庫本での再読です。やはりこのような本がらみあるいはイタリアの小さな村についての話は興味がわきます。観光地は有名なところがいくつもありますが、このようなところについてしかもすばらしい写真入りでの生活などを紹介してくれますと行きたくなります。2022/07/13
あきら
87
素晴らしい本に出会えました。 知識としても、思考としても、嗜好としても、とても良いものを吸収できたなと。 本を運んだ先人に敬意を感じる文体と、あえてタイトルが付けられていないだろう沢山の写真の数々から、それらがゆっくりと染み込んでいきました。 2022/02/03
rico
85
旅をした。ベネチアの古書店から始まり、行商人として本を売り歩いた山間の小さな村の人々の足跡をたどる旅。巡礼の道であり交通の要所だったこと、豊かな土地ではなかったこと。生きるために「そうした」理由は確かにあるけれど。知識や思想、夢、本と出会う喜び。彼らがもたらしたものの豊かさは、イタリアという国の土台の一部になったのかもしれない。この村につながる多くの人々は今も本に関わっている。本を、そして故郷を愛している。村の行商人の像は、凛々しく誇らしげだ。この村があって、こんな人たちがいる。本の力、信じてみたくなる。2024/05/16
ひさか
83
2017年6月〜12月方丈社HP連載「本が生まれた村」の10編に書き下ろしの6編を加えで2018年4月方丈社刊。2021年11月構成を一部変更の上、写真数点を加え、文庫版あとがきを追加して、文春文庫化。イタリアの本の文化と歴史を追いかけた内田洋子さんのエッセイ風ノンフィクション。文化の書、禁断の書、武器としての書などを行商で伝え、出版をも手がけて行くという話もさることながら、内田さんが、人と本との導きで、次々と新たな世界を発掘していく過程が楽しい。2023/04/20