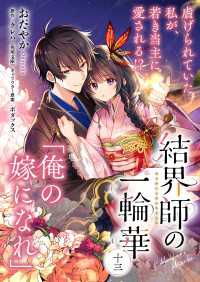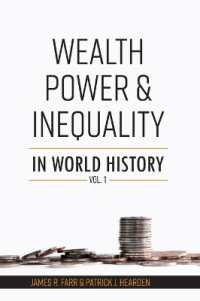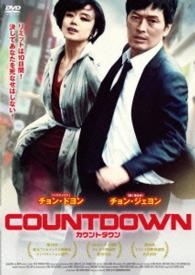出版社内容情報
1999年のラスベガス。ソニーは絶頂期にあるように見えた。しかし、舞台上でCEOの出井伸之がお披露目した「ウォークマン」の次世代商品は、二つの部門がそれぞれ別個に開発した、二つの互換性のない商品だった。それはソニーの後の凋落を予告するものだった。
世界の金融システムがメルトダウンし、デジタル版ウォークマンの覇権をめぐる戦いでソニーがアップルに完敗し、ニューヨーク市役所が効率的に市民サービスを提供できない背景には、共通の原因がある。それは何か――。謎かけのようなこの問いに、文化人類学者という特異な経歴を持つ、FT紙きってのジャーナリストが挑む。
企業であれ自治体であれ、高度に技術が発達している現代、あらゆる組織は「サイロ化」という罠に陥りがちである。分業化したそれぞれの部門が、それぞれの持つ情報や技術を部署の中だけでとどめてしまい、隣の部署とのあいだにも壁を作ってしまう。日本語では「タコツボ化」と呼ばれるこの現象は、どんな組織でも普遍的に存在するのだ。
経済学的な観点からすれば、身内での無駄な競争を生むような「サイロ」は、とにかく有害で無駄なものであるから、トップが「サイロ撲滅」の掛け声をかければ解決に向かう、と思いがちだ。ソニーの新しい経営者・ストリンガーも最初はそう考えた。しかし、彼は失敗した。壁は極めて強固で、一度できたサイロは容易には壊れない。
文化人類学者の視点を持つ著者は、「サイロ」が出来上がるには人間に普遍な原因があり、そのメカニズムを解き明かすところから始まる、と説く。人間に求められる技術が高度で専門的になればなるほど、サイロはむしろ必要とされるからだ。
人間は必ずサイロを作る、ならば、その利点を活用しつつ、その弊害を軽減する方法を探ろうとする画期的な論考が、本書である。
内容説明
専門的な技術を扱う部署が、周囲に壁を作り「サイロ」と化す。企業全体の衰退を招く危険な罠、それは、社会が高度になるほど、深く大きくなる。先端企業ソニー、大都市ニューヨーク―人の作るあらゆる組織に付き物の罠からの脱出法はあるのか?文化人類学者の顔を持つジャーナリストが解決法を探る!
目次
なぜ、私たちは自分たちが何も見えていないことに気がつかないのか?
ブルームバーグ市長の特命事項
第1部 サイロ(人類学はサイロをあぶり出す;ソニーのたこつぼ;UBSはなぜ危機を理解できなかったのか?;経済学者たちはなぜ間違えたのか?)
第2部 サイロ・バスターズ(殺人予報地図の作成;フェイスブックがソニーにならなかった理由;病院の専門を廃止する;サイロを利用して儲ける;点と点をつなげる)
著者等紹介
テット,ジリアン[テット,ジリアン] [Tett,Gillian]
1967年イギリス生まれ。ケンブリッジ大学で社会人類学を専攻。タジキスタンでの学究生活を終えた後、フィナンシャル・タイムズ紙の特派員となりジャーナリストの道を歩む。2000年より同紙東京支局長、2010年から12年まで同紙アメリカ版編集長。2015年ランカスター大学より名誉博士号を授与
土方奈美[ヒジカタナミ]
日本経済新聞記者を経て、2008年より翻訳家として独立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
owlsoul
たつなみそう
スプリント
konomichi
Mark X Japan