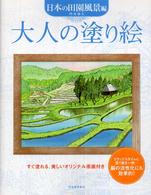出版社内容情報
快楽と不安の二項対立。修道院の奇妙な実験。恐怖を感じない女。成長するタクシー運転手の海馬。脳科学が明らかにする驚異の世界。
内容説明
人生の明るい面に目がいくか、暗い面に目がいくか。その差は脳の活動パターン自体に関連していた。エジソン、チャーチル、マンデラ…逆境に打ち勝つ偉人はみな「楽観主義者」。“楽観脳”と“悲観脳”は何が違うのか、心理学、分子遺伝学、神経科学を横断しながら人格形成の神秘を明らかにする「白熱教室」。
目次
序章 なぜ前向きな性格と後ろ向きな性格があるのだろう
第1章 快楽と不安の二項対立
第2章 修道院の奇妙な実験
第3章 恐怖を感じない女
第4章 遺伝子が性格を決めるのか
第5章 タクシー運転手の海馬は成長する
第6章 抑うつを科学で癒す可能性
著者等紹介
フォックス,エレーヌ[フォックス,エレーヌ] [Fox,Elaine]
心理学者、神経科学者。エセックス大学を経て、教授としてオックスフォード大学・感情神経科学センターを率いる
森内薫[モリウチカオル]
翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 民法学における伝統と変革---金山直樹…
-

- 電子書籍
- 上場廃止ラッシュ(週刊ダイヤモンド 2…