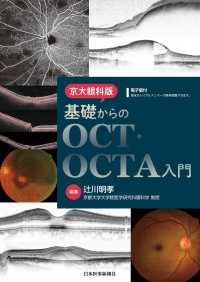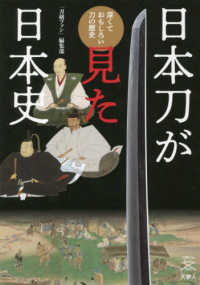出版社内容情報
江戸に生きた3人の清冽な日本人の人生を、人気歴史家が資料をもとに緻密に描きあげた感涙必至の物語。真に偉い人物がここに!
感涙必至! 人気歴史家が描く、美しい日本人
江戸に生きた3人の清冽な日本人の人生を、人気歴史家が資料をもとに緻密に描きあげた感涙必至の物語。真に偉い人物がここに!
内容説明
貧しい宿場町の行く末を心底から憂う商人・穀田屋十三郎が同志と出会い、心願成就のためには自らの破産も一家離散も辞さない決意を固めた時、奇跡への道は開かれた―無名の、ふつうの江戸人に宿っていた深い哲学と、中根東里、大田垣蓮月ら三人の生きざまを通して「日本人の幸福」を発見した感動の傑作評伝。
目次
穀田屋十三郎
中根東里
大田垣蓮月
著者等紹介
磯田道史[イソダミチフミ]
1970年、岡山県生まれ。2002年、慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(史学)。現在、静岡文化芸術大学教授。史料を読みこみ、社会経済史的な知見を活かして、歴史上の人物の精神を再現する仕事をつづけている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 5件/全5件
- 評価
テレビで紹介された本・雑誌の本棚
- 評価
-





hide-books本棚
- 評価
新聞書評(2017年)の本棚
- 評価
仕事と通勤の隙間に、少しだけ世の中を考える本棚
- 評価
新聞書評(2020年1月~3月)の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐々陽太朗(K.Tsubota)
152
中世から江戸時代にかけて武士道が確立されていく中で「人は一代、名は末代」といいながら、後世に名を残し子々孫々の繁栄を願う行動様式こそ日本の心の美しさの原点であろう。そうした心は為政者、権力者に利用されてきたという見方もあろう。しかし私はそのような見方をすべきではないと思う。そのような見方は気高く美しい心を持ってした行為を貶めるものだろう。事実、江戸時代、支配階級であった武士のおおかたは身分の低い町民よりも貧しく質素な生活をしていたのであり、諸外国の支配階級のように人民からの搾取で生きていたのではない。2016/05/06
Makoto Yamamoto
146
『殿、利息でござる』の映画を見て、実話であり原作があるとのことだった。 その原作は『無私の日本人』第一話の「穀田屋十三郎」は映画とほぼ同じストリー。本家の浅野甚内も素晴らしい。 第二話「中根東里」は彼の才能と荻生徂徠のいやらしが目についた。 第三話「大田垣連月」和歌で名前を憶えていたが、改めてその人生の壮絶さを読ませてもらった。 いい話だった。 2020/04/22
むーちゃん
143
歴史に埋もれた無私の日本人三人のことが書かれています。古文書が読むことができることで、このような素晴らしい人を発掘し、紹介してくれるのは素敵なことです。 2019/10/07
あすなろ@no book, no life.
137
果たして領民が領主に金を貸し付け、利金を取り続け、役儀をまけてもらうなとということが可能か?実史に基づく作品。中世日本人に宿る精神を解きながら語るこの史実。なかなか読み応えあり、良質な読書タイムでした。磯田氏は、武士に家計簿しか読んだことはないが、別の作品も手にとってみよう。無私の日本人、なかなか含蓄あるタイトルだった。江戸時代中期〜第二次大戦迄続く日本人の精神を解いたものだが、否、ほぼ、現代の日本人にも同様の精神はあるのでは?悪所のみならそれは哀しい。2016/08/16
またおやぢ
134
『願はくは のちの蓮の花の上に 曇らぬ月を みるよしもがな』歴史の中に埋もていた先人に焦点をあて、彼らの生き様を語ることで、この国で暮らしていた人間の哲学と知恵を見いだそうとした意欲作。その時代の人々全員が「無私」の心をもっていた訳ではないだろう。しかし、皆が貧しかったからこそ、物質的な豊さとは異なるところに幸福を見つけざるを得なかったに違いない。一方、物が溢れる現代に暮らす我々は、物的な豊さは即ち幸福ではないと気づいている。不確実な世の中にあって、自らの存在価値を問い、精神の安寧の道標となる一冊。2016/10/12