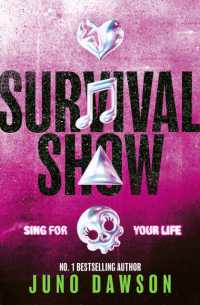内容説明
「ペイリーさんの小説は、とにかくひとつ残らず自分の手で訳してみたい」と村上氏が語る、アメリカ文学のカリスマにして伝説の女性作家の第一作品集。キッチン・テーブルでこつこつと書き継がれた、とてつもなくタフでシャープで、しかも温かく、滋味豊かな十篇。巻末にデビュー当時を語ったエッセイと訳者による詳細な解題付き。
著者等紹介
ペイリー,グレイス[ペイリー,グレイス][Paley,Grace]
1922~2007。1922年ニューヨーク生まれ。ロシアからのユダヤ系移民の家庭に育つ。詩人として創作活動を始め、59年に短篇集「人生のちょっとした煩い」を発表、74年「最後の瞬間のすごく大きな変化」、85年“Later the Same Day(その日、もっとあとで)”の3冊により作家としての名声を確立、アメリカ文学シーンのカリスマ的存在となった。2007年8月、84歳で永眠
村上春樹[ムラカミハルキ]
昭和24(1949)年京都市生まれ。作家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ミカママ
481
春樹さまの『翻訳夜話』を読んで「そういや彼の翻訳作品がイッコ積んであったな」と手に取る。大好きなホッパーが表紙で、期待も高まる。結論からいえば、これは硬いかなぁ。当時の主婦作家がキッチンテーブルの上で書いた作品には好きなものが多いけれど、この作家さん目線の日常がわたしたちのそれとかけ離れている、というか。村上さんも柴田さんも訳に苦労なさったのでは。『人生への関心』はちょっといい。2024/01/20
ヴェネツィア
252
グレイス・ベイリーの最初の短篇集。訳者の村上春樹はあとがきでは全く言及していない作品なのだが、私が篇中でニューヨークに住むユダヤ人女性作家らしさが最も出ていると思うのは「いちばん大きな声」だ。この作品の視点人物は、小学校高学年のシャーリーだが、彼女は学校でのページェント(降誕劇)で、声の大きさを買われてプロンプター(?)に抜擢される。ところが、ユダヤ教徒である彼女にとって、そして彼女の家族にとっても、クリスマスは聖なる日ではなかったのだ。この文化ギャップが、彼女の作品の基調には常にあるのではないだろうか。2013/02/01
こばまり
56
嗚呼、人生とは酸いものよ。いずれの登場人物も、等しく目の下にぼっこりクマがありそうだ。それにしても何と風変わりな作風なのだろう。ナンダコレナンダコレとおろおろしながら読了。2017/05/25
nemuro
50
『矜持 ~警察小説傑作選~』(今野敏ほか/PHP文芸文庫)に続く“しりとり読書”の139冊目。ブログ(アメブロ&ジュゲム)内を検索したら、網走時代、2014年9月「ひかりや書店網走店」にて、『下流志向』(内田樹/講談社文庫)、『世界にひとつだけの本』(北阪昌人/PHP文芸文庫)と、3冊での購入だった。「アメリカ文学のカリスマにして伝説の女性作家の(世に出ている短篇小説集3冊のうちの)第一作品集」。それなりに分かる作品もあれば分からないものもあって。巻末、デビュー当時を語ったエッセイが分かりやすくて面白い。2025/10/24
ばう
49
★ ★「ああ、ちょっと昔のアメリカの短編小説を読んだ」というのが1番の印象です。作者がロシアからのユダヤ系移民の家に生まれた方だからか、人種問題とそれに付随する宗教問題が時々チラリと顔を覗かせる気がします。どの短編も等身大の、アメリカのどこにでもありそうな話だけれど全体的に何だかクリアじゃない不思議な世界を見ている様な気分になりました。文体のせいかな?後半はさらっと読んでしまいましたが好きな人はハマるかも。私は…同じ作者の作品をもう一冊読むか?と聞かれたら、直ぐには読まないというレベルでしょうか?2020/07/01
-

- 和書
- 謎のヴァイオリン