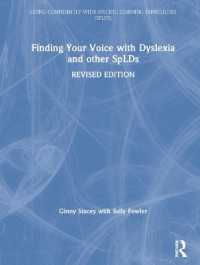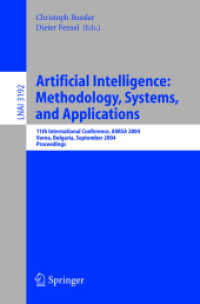内容説明
日本文化の深層を探ると―。能・歌舞伎・人形浄瑠璃から各種の工芸にいたるまで賎視された人々が、その基底を支えてきた。紀州湯浅の門付け芸・春駒。巡業三百年、鳥取・円通寺のデコ舞わし。日本有数の歴史を誇る三次の鵜飼。民俗技芸の起源をたどり、苛烈な差別をはねのけ力強く生き抜く民の実像を伝える。
目次
序章 古い歴史のある部落を歩く(日本文化の深層を掘る;『小栗判官』『葛の葉』伝説の街道筋)
1章 熊野街道筋に残る民俗芸能(海沿いでも部落には漁業権はなかった;熊野詣で賑わった宿駅 ほか)
2章 デコ舞わし巡業の三百年(雪の夜のすすり泣くような胡弓の音;河原で催された勧進興行 ほか)
3章 鵜飼で生きる川の民(「川の民」として生きた被差別部落;賎視された「鵜飼」の民 ほか)
終章 日本文化の地下伏流(街道を往来した遊芸民;山間の寒村を訪れた遊行者 ほか)
著者等紹介
沖浦和光[オキウラカズテル]
1927年、大阪生まれ。東京大学文学部卒業。比較文化論、社会思想史専攻。桃山学院大学名誉教授。日本各地の数多くの被差別部落を歩き、日本文化の基層を探る研究を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
つちのこ
34
生業と居住環境に関わる厳しい差別が原点にある部落問題の中で、人間としての生が輝く側面、それが伝統的な民俗である民衆文化だ。我が国の至宝ともいえる最高の芸術の域まで高めた歌舞伎や人形浄瑠璃も、その原点には差別されてきた人々の生業からなっている。本書で紹介されたデコ舞わしや鵜飼も然り。田畑や漁業権を持たぬ搾取されてきた人々の生きていく糧として生まれ、伝統に発展したものである。著者は差別と抑圧に闘った歴史を“豊饒の闇”と書く。その的を得た表現に感嘆。幼き頃の正月の風物詩だった獅子舞の姿を、もはや見ることはない。2022/08/20
fseigojp
9
沖浦さんと網野さんの差異をAIは 「沖浦和光氏は、被差別民や部落問題の構造的な側面(社会構造、政治的な側面)を重視する一方、網野善彦氏は、中世に遡る地域的な差異や、非農業民の社会的な存在様式に焦点を当てて、部落の起源を中世に求めるという説を提唱し」と述べている ふーん2025/05/26
Nunokawa Takaki
2
昔から差別されながらも懸命に生きてきた人たちがいる。彼らが作り出してきた芸能や文化は今でもノスタルジックな日本を思い出させてくれる。春駒、デコ舞わし、鵜飼い、どれも過酷な生活の中で生まれてきた知恵そのもののようだ。もうどれも話で聞く以外見ることなど皆無だろうが、想像力を働かせれば、当時の風景、人々の暮らしが目の前に現れてくる。現代はもっと贅沢にはなったが、それは、人とのつながり、ふれあいといった部分と引き換えに得られたものだ。ならばどのように生きねばならないのか、考えなければならない。2015/04/30
りんか
1
本書で扱うのは豊かな耕作地や漁業権を持たなかった、持てなかった集団が生活のため身に付けた芸能。芸能そのものよりも被差別部落の生業記録の印象が強い。2013/10/23
-

- 電子書籍
- 龍の花贄~生贄の私が幸せになるまで~ …