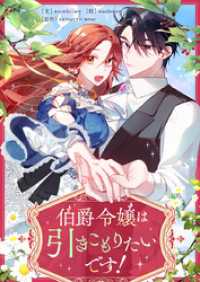内容説明
十二月を「師走」というその語源は「年末は忙しく先生までも走る」から、「塩梅(あんばい)」とは昔は塩と梅で味つけしたからとか、尤もらしく言われているけれど…漢字語源の俗説をついた連作をはじめ、名前にちなむ愉快な話、井伏鱒二が『唐詩選』から『臼挽歌』をへて名作『厄除け詩集』を作った経緯など、面白エッセイが満載。
目次
ウマイとオイシイ
漢字語源の筋ちがい
ドンマ乗りとカンカンけり
訳がワケとはワケがわからぬ
お客さまは神さまです
ヒロシとは俺のことかと菊池寛
「サヨナラ」ダケガ人生ダ
著者等紹介
高島俊男[タカシマトシオ]
1937年生れ、兵庫県相生出身。東京大学大学院修了。中国文学専攻。主な著書に『水滸伝と日本人』(第5回大衆文学研究賞)、『本が好き、悪口言うのはもっと好き』(第11回講談社エッセイ賞)、『漱石の夏やすみ』(第52回読売文学賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
91
7作目の再読です。いつも忘れてしまっていることが多く、再読によってまた知識の再構築のような感じが頭の中で行こなわれています。知識量の多いエッセイでとくに言葉関連が多いのでたのしめます。「勉強しまっせ」というところでは、コマーシャルの言葉から鴎外の勉強という言葉について敷衍されています。徳川慶喜を「よしのぶ」か「けいき」と呼ぶのかでの論争なども楽しめます。2024/11/27
KAZOO
11
2001年から2002年に掲載されたものを集めています。いつもながら、言葉や漢字についてのこだわりはすごいなあと感心しています。今はもう連載されていないのですが、よく週刊誌に連載されていたと読んでみて思います。また読者からの指摘などを「あとからひとこと」ということで、掲載されているのも、筆者の性格をよく表していると感じます。2014/04/16
モリータ
8
◆連続で読むと筆者の考え方が身に着いてきたように思う(日本固有語と漢字の関係、文語の表記など)。◆連載内外で古田東朔先生や宮崎修二朗氏との交流があるというのにはウーム。◆本巻末の「「サヨナラ」ダケガ人生ダ」の項は特に面白かった。井伏鱒二による漢詩の訳として名高い「厄除け詩集」には、種本として江戸時代の俳人・潜魚庵の訳(異本3種)があったこと、林芙美子との因島訪問から于武陵「勧酒」の井伏オリジナルの訳ができたことなど。◆研究そのものではないとしても、週刊文春でこの内容の連載は読みごたえがあっただろう。2020/06/02
さりゅ
5
高島先生のこだわりは、いつもながら凄まじいです。名前と井伏鱒二のテーマの話が個人的には面白かった。平賀元義の歌にはニヤニヤしました。2014/09/21
Gen Kato
3
何の気なしに言葉を使うのが怖くなる。蛍の光、「サキクトバカリ、ウトウナリ」って30年前に教わったよなあ…(間違ってた)。しかし某小説家さんの用語の誤り、不思議ですね。校閲者は仕事しなかったんだろうか…2015/09/08