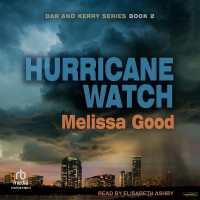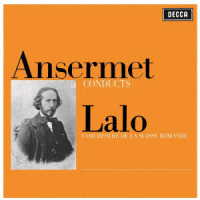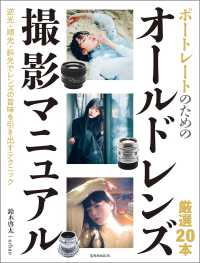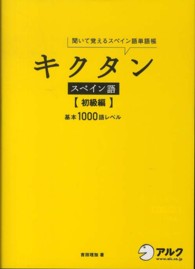内容説明
菊池寛先生の秘書になった「わたし」。流行のモガ・ファッションで社長室に行くと、先生はいつも帯をずり落としそうにしてます。創刊された「モダン日本」編集部では、朝鮮から来た美青年・馬海松さんが、またわたしをからかうの―。昭和初年、日本の社会が大変貌をとげる中で、菊池が唱えた「王国」とは何だったのか。
目次
忙中閑、ありやなしや
謎の美青年
かそけきモダン
白い蛇の行方
霜月酉の市
粋な黒塀
荒浪の音
悪戯と傷
接吻せず
木村屋のジャムパン
焦燥の京都
葬式に行かぬ訳
夏目漱石の一件
曇天の風景
憧れの愛蘭土
土曜日のマチネ
淋しい遊民
十年後の日本
滅びの予感
王の孤独
著者等紹介
猪瀬直樹[イノセナオキ]
作家。1946年、長野県生まれ。『ミカドの肖像』(86年)で大宅壮一ノンフィクション賞受賞。『日本国の研究』(97年。文藝春秋読者賞受賞)は、政界の利権、腐敗、官僚支配の問題を鋭く突き、小泉首相から行革断行評議会委員、道路公団民営化推進委員に任命される契機ともなった。また、メールマガジン「日本国の研究」を主宰、政府税制調査会委員、東京工業大学特任教授など幅広い領域で活躍。2007年6月、東京都副知事に就任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
駄目男
17
あれは何年前だったか、もう7年ぐらいにはなるか、讃岐の国、高松に行ったことがある。ついでといっては何だが菊池寛記念館に寄ったのだが、何と、独立した建物ではなく図書館内にあるではないか。生家跡にも石碑が一本立つのみで、天下の菊池寛にしては情けない扱い。以前、川端康成記念館に行った時と同じような待遇で驚いた。その時、図書館で無料配布の古書の中に『半自叙伝』があったので貰ってきた。本書は菊池の秘書となった「わたし」が、『半自叙伝』を読み解いていく中で菊池の半生を紐解いていくような内容だ。著者の猪瀬直樹は政治家2024/10/05
エドワード
17
文藝春秋の創始者菊池寛を秘書の目から描く物語。浅草竜泉寺町に生まれた下町っ子の彼女が、内幸町のオフィスではモガに大変身。<流れている風の匂いが明らかに違う町をものすごいスピードで往復しているのです。>昭和初期のモダン東京を見聞する時に感じる不思議感が「よそゆきのモダン」という言葉で的確に表現される。外では背広、家では着物。すき焼きもコロッケも日本の味だ。文士という人種のいた時代の楽しき哉。菊池寛のユーモラスな人間性が垣間見えて興味深い。猪瀬直樹さん、結構好きだったんだけど、今どうされているのかな。2015/07/16
makoto018
11
「文豪、社長になる」ならの流れで再読。ノンフィクション作家・猪瀬直樹だが、こちらはフィクションを交えた作品。モデルはいるものの、私設女性秘書の眼を通して描くもの。大正、昭和初期から戦中までの時代を描くほうが比重が多めか。モダンガールとマルクスボーイが闊歩する戦前の東京。作家菊池寛としては、中に閉じこもる文学ではなく読者に開けた小説であり、一言一句に呻吟するよりも、誤字を恐れず物語をどんどん進めるあたりは現代につながる。文藝春秋は今でも健在だし、昼ドラ真珠夫人のヒットや文春砲も記憶に新しく、まさに不易流行。2023/08/12
relaxopenenjoy
4
図書館でたまたま。文春100周年記念作に続き、菊池寛絡みの本を見つけて。あの猪瀬元知事が作家とは知りませんでした。主人公(わたし)若くてモダンガールな菊池寛の秘書と、先生とのロマンス(フィクション?)、朝鮮から来た青年(マーさん)も絡まり。「わたし」のモデルは佐藤碧子さん。浅草 入谷 鷲(おおとり)神社の酉の市。 2025/08/16
onaka
4
個人秘書として雇われていた女性視点から見た菊池寛の来歴と深層が、朝鮮人の青年編集者との関係も絡めながら明らかになって行く。高等遊民の虚無や自我を描くのではない、生活意志に根差した文学であるべきという強烈な指向があり、それを世に広める手段として出版社の創業があった。モダンな世界に向かって爪先立ちしていた当時の日本社会を背景に展開される三角関係の起伏もあり、単なるノンフィクションにはない没入感がある。猪瀬さんの作品ではおそらく唯一の女性一人称による語り口が新鮮な、なかなかの一品です。2013/03/14