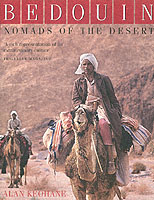内容説明
原っぱや露地では、べーごまやめんこで遊ぶ子どもたちの声が響き、家には夕餉の支度に忙しい割烹着姿の母親がいた―。名文家二人のエッセイと60点以上の写真で甦る昭和の暮らし。山本氏は「下宿屋」「蕎麦屋」などを引き合いに戦前の東京を描き、久世氏は「日傘」「七輪」などから暮らしの四季を点描、巻末対談で大いに語り合う。
目次
第1部 戦前を見に行く(山本夏彦)(不忍の池;下宿屋;アパート;髪床;質屋 ほか)
第2部 過ぎ行く季節のなかで(久世光彦)(産湯;割烹着;姫鏡台;入学式;大食堂 ほか)
第3部 昭和恋々 記憶のなかの風景―対談・山本夏彦×久世光彦
著者等紹介
山本夏彦[ヤマモトナツヒコ]
大正4(1915)年、東京下谷根岸生まれ。24歳のとき名作「年を歴た鰐の話」の翻訳を『中央公論』に発表。戦後『室内』を創刊し、同誌に「日常茶飯事」、『文芸春秋』に「愚図の大いそがし」、『諸君!』に「笑わぬでもなし」、『週刊新潮』に「夏彦の写真コラム」を連載中。昭和59年に菊池寛賞、平成2年に「無想庵物語」で読売文学賞を受賞した
久世光彦[クゼテルヒコ]
昭和10(1935)年、東京生まれ。東京大学文学部美学科卒業後、TBSに入社。「時間ですよ」「寺内貫太郎一家」等を手がける。退社後カノックスを設立し、平成4年、「女正月」他の演出で芸術選奨文部大臣賞受賞。5年、「蝶とヒットラー」でドゥマゴ文学賞、6年、「一九三四年冬―乱歩」で山本周五郎賞、9年、「聖なる春」で芸術選奨文部大臣賞、13年、「蕭々館日録」で泉鏡花文学賞を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
双海(ふたみ)
sasha
skellig@topsy-turvy
倍の倍のファイト倍倍ファイトそっくりおじさん・寺
Haruka Fukuhara
-

- 電子書籍
- 幼馴染はダサビッチ 第164話 伝えた…