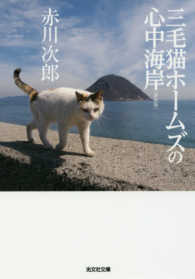内容説明
戦争文学の「幻の名作」として本篇ほど長く文庫化が待望された作品はない。中国雲南の玉砕戦から奇跡の生還をし、郷里で老いてゆく二人の兵士。戦争とは何か。そして国家とは?答えられぬ問いを反復し、日々風化する記憶を紡ぎ、生と死のかたちを静謐に語る。この稀有な作家でなければ到達しえなかった清澄な文学世界である。
著者等紹介
古山高麗雄[フルヤマコマオ]
1920年、旧朝鮮新義州生まれ。旧制三高中退後、応召。ビルマ、雲南、サイゴンなど万年一等兵として大東亜をまさに転々。1970年「プレオー8の夜明け」で第63回芥川賞受賞。1973年「小さな市街図」で第23回芸術選奨文部大臣新人賞受賞。1994年「セミの追憶」で第21回川端康成文学賞受賞。2000年「断作戦」「龍陵会戦」「フーコン戦記」の三部作により第48回菊池寛賞を受賞する。2002年3月逝去。享年81
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しんこい
11
地図もないので中国奥地のどこでいったい何の作戦をやっているのかさっぱりわからず断片を知るのみなのだが、戦場にいた兵士にわかっていた状況も結局こんな断片だったんだろう。雲南なんて今の時世でもめったに日本人がいかないだろうに、そんなところで戦争していたのだからすさまじい。2018/05/31
みや
7
雲南戦線の主役である龍兵団の数少ない生還者に取材した戦争小説。拉孟や騰越の激戦と全滅は、寡聞にして知らなかった。守備隊の奮闘及ばず、遠征軍に徐々に圧されていく様に息を呑む。しかし、後から読めば絶望的に勝ち目のない攻防。皆、どこか気が違ってしまっていたとしか言いようがない。日本兵の遺体や捕虜に対する中国兵たちの礼節ある振る舞いに救われる。昭和50年代になり、使命感にかられて亡き戦友の遺族を訪ね、微妙な応対をされるところまでが本作のポイント。2022/08/15
無理矢理読書会@半田建設
7
断作戦とは日本軍が英中の攻勢によりビルマ北部を失った後も国民党への物資支援ルートを遮断し続けることを目的とした。断作戦については昔のカナ交り文で中盤出てくるが意味が分からずインターネットで調べて理解。拉孟、謄越、龍陵守備隊の数少ない帰還兵2人が兵卒の書いた戦記を残そうと回想する形で話は進んでいく。勝利の盛り上がりは当然なく、淡々と語られる船上での思いにやるせなさを感じた。2020/04/07
おとん707
4
太平洋戦争の戦記小説は今までにもいくつか読んだが、多くは著者自身が一人称で語ったものだった。その場合、気のせいかもしれないが、どうしてもその記述の中に著者自身の行動が美化されているのを僅かに感じてしまうのだった。古山高麗雄も自分自身が下級兵として雲南省で戦闘を体験しているが、本書では自らの体験でなく戦後復員した第三者の下級兵士が体験記を著す過程を通じて戦争を語っている。そこには誇張も美化もない誠実な描写がある。それがかえって戦争の無意味さを訴える。著者の反戦の訴えはこうして静かに読者に沁みわたる。2019/08/17
やご
1
第二次世界大戦中の1944年、中国雲南の街・騰越で十数倍の兵力による連合国側の攻撃を受けて玉砕した日本軍守備隊の戦いを、数少ない生き残りが戦後三十数年を経て平穏な暮らしの中、時の流れを感じつつ追憶するという形で描いた戦記文学。形式としては小説ですが、実際に騰越守備隊に所属していた方を取材して書かれており、ノンフィクションに近いものと考えてよいのでしょうか。 (続く)→ https://gok.0j0.jp/nissi/0204.htm2008/02/10
-
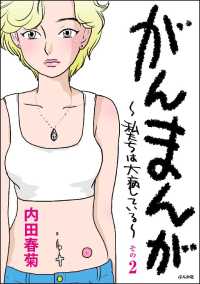
- 電子書籍
- がんまんが~私たちは大病している~(分…
-
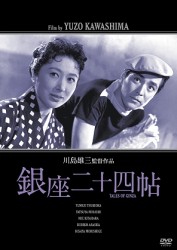
- DVD
- 銀座二十四帖