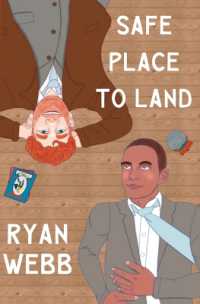出版社内容情報
岩倉は孝明天皇毒殺の首謀者なのか──「尊皇攘夷」「佐幕」といった言葉を剥きながら、新たな岩倉像を立ち上げた永井文学の神髄。
内容説明
明治維新の立役者の一人、岩倉具視。下級公家に生まれ、クーデターの画策などで何度も追放されながら、いかに権力の中枢にのし上がったのか。長年構想を温めてきた著者が、卓越した分析力と溢れる好奇心で史料と対峙。「尊王攘夷」「佐幕」といった言葉を剥きながら、新たな岩倉像を立ち上げた永井文学の集大成。第50回毎日芸術賞受賞。
目次
貧弱な構図
虚妄の世界
手入の風景
奔馬
皇女・皇女
奈落
姦物の時間
情報の虚実
毒殺・そして「壁」の光景
「深謀の人」の「記憶」
その日まで
余白に…
著者等紹介
永井路子[ナガイミチコ]
大正14(1925)年、東京に生れる。東京女子大学国語専攻部卒業。小学館勤務を経て文筆業に入る。昭和40年、「炎環」で第52回直木賞受賞。57年、「氷輪」で女流文学賞受賞。59年、第32回菊池寛賞受賞。63年、「雲と風と」で吉川英治文学賞受賞。平成21年、「岩倉具視」で第50回毎日芸術賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kitten
17
嫁の蔵書から。明治維新の英雄、公家として上り詰めた岩倉具視。なんとなく歴史上で出て来るけれども、この人がどういう人だったのか全く知らなかった。もともと、下級の公家だったけど、天皇とお近づきになったことで力をもっていった。そして、権謀術数の人。明治新政府を作った立役者の一人なんだ。のちの「岩倉使節団」が有名だけど、あれは実質的に失敗で何もしていない。政策、理念もあっただろうけど、それよりも執念の方を感じたな。岩倉使節団の話も読んでみたい。2021/07/08
花林糖
14
岩倉具視の生涯を描いた伝記ではなく評伝。歴史小説と思い読み始めたらあれ?読み慣れるのに少し苦戦しました。幕末の公家、外様大名の長年の恨み、徳川家の争いなど、幕末の緊迫した様子が描かれていて興味深く読了。孝明天皇の毒殺説、中川宮も登場。維新後は駆け足。巻末のあとがきも良かった。(岩倉具視=150石の下級公家から5000石の右大臣へ)2024/09/02
やいっち
13
幕末から維新にかけては、幕閣も将軍も天皇も諸大名も上級武士も下級武士も、町人も商人、農民も、それぞれに表立って、あるいは陰で活躍し、暗躍し、語られぬドラマとして消え去っていったのだろう。 小生の畏敬する島崎藤村の、「木曾路はすべて山の中である」の書き出しで知られる『夜明け前』は、まさに激動し激変する幕末の怒涛の動きに翻弄される、生真面目な村の本陣・庄屋の当主の苦悩と絶望に至る物語だ。 恐らくは、当時、日本中に大なり小なり、そういった時代に翻弄された人々が居たに違いない。 2016/10/28
sagatak
13
言葉の皮を剥ぎながらというサブタイトルに期待感を持って読む。尊皇、攘夷など以前から実態とは合わないと思っていたので納得いく説明だった。慶喜の大政奉還、その後の王政復古は彼の英断もあったかと思っていたが勘違いだった。虚々実々の駆引きの世界でした。新政府の政策も言葉にうまく皮を被せながら騙し騙し大名、公家らの力を削いでいく。現代の官僚政治に繋がると思う。TPPのことなど考えた。2014/09/04
日の光と暁の藍
10
岩倉具視の小説というより、岩倉具視や明治維新を巡るテーマを章ごとに区切ってまとめた歴史エッセイという印象。副題の言葉の皮を剥くとは、歴史を語る際に用いられる言葉が、実態を理解していないまま言葉の一人歩きを許している現状を嘆き、その実態を明らかにする試みのこと。興味深かったのは「手入の風景」の章。江戸時代の手入とは、贈賄のことを意味する。その手入で大失敗をしたのが堀田正睦だという。また、天皇の意見を左右するほどの文書内覧という権利の存在なども初めて知ることが出来た。歴史知識の不足を感じたので、再読したい。2018/07/22