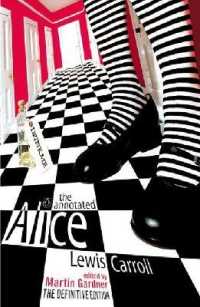出版社内容情報
一汁一菜に甘んじつつ財政改革に心血そそいだ上杉鷹山と執政たちの無私の心と苦悩を描き、藤沢さんの遺書とさえよばれた傑作長篇
内容説明
天よ、いつまでわれらをくるしめるつもりですか。改革はままならない。鷹山の孤独と哀しみを明澄な筆でえがきだす下巻。けれど漆は生長し熟しはじめていた。その実は触れあって枝先でからからと音をたてるだろう。秋の野はその音でみたされるだろう―。物語は、いよいよふかく静かな響きをたたえはじめる。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
315
上巻では治憲も若く、借金苦の渦中にあったとはいえ、当綱等の積極策による活力に溢れてもいた。したがって物語にも随所に躍動感が感じられたのである。ところが、下巻ではさらに困窮の度は増し、藩財政の再建策も思ったようには実を結ばない。そして、藤沢の物語作法は一層フィクションを離れ歴史小説への傾斜を見せる。結末はさらに60枚程が書かれるはずであったらしいが、藤沢の死によって絶筆となった。それはまさに晩年の鷹山の姿とも重なるが、どうすることもできない人間の宿命を受け入れた諦観の行き着く姿であったようにも思われる。2015/12/29
とん大西
128
切実だ、というか鬱々とした気持ちに。貧困とはなんと辛いことか。不作、凶作、大飢饉。江戸中期の寒村の有り様、名門意識を脱しきれない小藩の苦悩が生々しく問いかけてくる。治世の源泉は農。農を生業とする民に慈しみを。理想を胸に政治改革に乗り出す鷹山。が、御家の為とは言いつつも一枚岩になれない家臣達。そして毎年気をもむ稲の実り。天気を憂い、いつしか空を見上げる癖がついていた鷹山。稀代の政治家でありながら、政策が全て大団円となったわけではない。寧ろままならず常に艱難辛苦に身を置いた日々。鷹山、苦悩の采配は未々続く。2023/05/07
ふじさん
89
細川平洲の教えを胸に、米沢藩の再興に励む上杉治憲に支えとなる家臣が二人、竹俣当綱と莅戸善政、だが改革は思う進まず、当綱は失職、善政は致仕し、ついには治憲も隠居することのなり、藩改革は数年に及び凶作もあり、藩は疲弊の一途を辿る、隠居した治憲は苦悶の日々か続く、そんな中再び莅戸善政が中老に返り咲き、藩改革に取り組むことになる。前回は、難しさに圧倒されたが、今回改めて読み返してみると、上杉鷹山の人物像の描写や米沢藩の苦悩が事細かに描かれていて読み応えがあった。藤沢周平の本は読む時によって読んだ感想が変わる。2025/11/11
goro@the_booby
82
上杉鷹山を追った作品。人となりが良く分かった。倹約ばかりが話題に上るが、自分の時代だけではなし得ずその後も米沢の地を何とかしようと見守り通した。緊縮財政だけでは人も疲れ倒れてしまうが、借金を重ねて殖産に励もうと希望を示した。漆の実から蝋を取ろうと画策したのだが結局は上手く行かなかったが、それでも見捨てなかった。見捨てられなかったのだろう。質素倹約だけの人ではなかったと藤沢は伝えたかったのかと思う。最後の作品。2022/01/25
mura_ユル活動
73
中々、読み進めませんでした。話題が難しかったのかも。時代小説で切り合いなしは久しぶり。米沢藩、経済と政治。幕府の普請手伝い、天候による米の不作凶作など藩が苦境に。どんよりとした空気がずっと続く。それがかえって現実感を浮かび上がらせることになっている。人物。世の中は人で動いていくのを実感。江戸時代、士風の退廃に垣間見るもの。倹約令にかかわらず、人々は消費を拡大へ。時代は変わる、変わっていく。竹俣当綱、上杉鷹山こと治憲、そして莅戸(のぞき)善政。藤沢さん晩年、入院中も本作品の執筆意欲は衰えなかった。 2014/08/09
-
- 洋書
- You Save Me