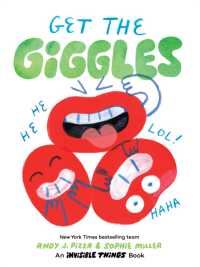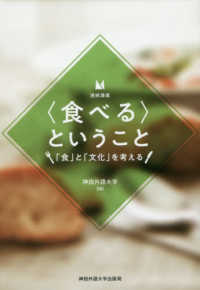内容説明
無名の陶芸家が生み出した美しい青磁の壷。売られ盗まれ、十余年後に作者と再会するまでに壷が映し出した数々の人生。定年退職後の虚無を味わう夫婦、戦前の上流社会を懐かしむ老婆、四十五年ぶりにスペインに帰郷する修道女、観察眼に自信を持つ美術評論家。人間の有為転変を鮮やかに描いた有吉文学の傑作。
著者等紹介
有吉佐和子[アリヨシサワコ]
昭和6(1931)年、和歌山生まれ。昭和31年に『地唄』で文壇デビュー。紀州を舞台にした『紀ノ川』『有田川』『日高川』三部作、世界初の全身麻酔手術を成功させた医者の嫁姑問題を描く『華岡青洲の妻』(女流文学賞)、老人介護問題に先鞭をつけ当時の流行語にもなった『恍惚の人』、公害問題を取り上げた『複合汚染』など意欲作を次々に発表し人気作家の地位を確固たるものにする。多彩かつ骨太、エンターテインメント性の高い傑作の数々を生み出した。昭和59年8月逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
826
全13話からなる連作短篇集。第1話から最後まで連関性を持ち、全体として円環を結ぶ構成をとっている。同時に各話の独立性も保たれつつ、表題の青い壺が物語の核として機能するという構造である。ただし、この壺は作者、庄造の畢生の作品なのだが、その扱われ方は各話さまざまである。どの短篇もなかなかによくできており面白いし、有吉佐和子の文体もまた古さも感じさせない。この作品群の一番の妙味は、やはり人物像の造型の確かさにあるだろう。さすがにヴェテランの練達の業を感じさせるのである。私は第9話が面白かったが、他もほぼ同等。2024/07/01
Nobu A
543
有吉佐和子著書9冊目。77年刊行。読書会課題図書。有吉佐和子が小説家だけでなく、劇作家及び演出家だと思い出せてくれる本書。数々の代表作のような時代の流れを描く大河小説や息を吹き込んだ歴史物語とは明らかに違う。人ではなく、青磁を巡ってそれに関わる人々の欲望、執着、虚栄心と言った様々な心情を静かに巧みに描写。流麗な筆致。特に第9話の老婆三人の諧謔的やり取りは面白く読んだ。所々時代を感じさせる描写があるが、今読んでも違和感がない点が本書の凄さ。正に時代を超えて読まれる秀作。有吉佐和子こそ国民的作家だと感じる。2025/12/11
Kotaro Nagai
440
有吉佐和子の長編は扱うテーマの重さゆえ手を出せないでいましたが、これは昭和51年文藝春秋1月号から52年2月号まで連載された連作短編集。著者40歳の作品。陶芸家の牧田が焼き上げた青磁の壺が狂言回しに次から次へと所有者が変わっていき、その所有者に関わる人間模様が描かれる。過去を懐かしむ老女の独白(第7話)は印象的な作品。2倍程度のボリュームで70歳を超えた老女たちの同級会を描く第9話も生き生き描いてこちらも好編。13編どれも鋭い人間観察が作品に生かされていると感じる。第13話で壺は作者の牧田の前に現れる。2023/11/11
bunmei
325
50年以上前の高度経済成長期に差し掛かる中、まだ戦後を一部では引きずっていた昭和を舞台とした、青い壺に纏わる13の短編集。戦後の復興を目指してきた昭和の人々の思いが、令和の今になって再燃している。物語の素材は、当時の日常の一部を切り取った出来事ばかり。その中に、人が決して表には見せない本音や心理をリアルに描写している所が、現代人に通じるものあるのだろう。そして、巡り巡ってその傍らに置かれ、人々の言動を見届けてきたのが、青磁の壺。其々の思いに寄り添いながら、その美しい光沢の中に人間模様を映し出していく。 2025/05/01
おばおば
310
★★★☆☆100分で名著で有吉佐和子さんのことを知りました。青い壺以外では、「恍惚の人」は知っていましたが読んだことはありませんでした。壺が巡っていく人々の間で起こる話ですが、私には第二話、五話、十三話が印象的でした。内容が時代を感じるところもあって良かったです。印象的に残った三話以外も今でも起こり得る内容でした。2025/03/12
-
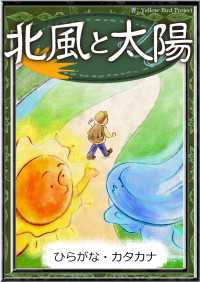
- 電子書籍
- 北風と太陽 【ひらがな・カタカナ】 き…