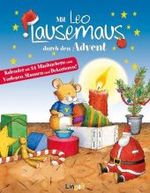内容説明
台湾撤兵以後、全国的に慢性化している士族の反乱気分を、政府は抑えかねていた。鹿児島の私学校の潰滅を狙う政府は、その戦略として前原一誠を頭目とする長州人集団を潰そうとする。川路利良が放つ密偵は萩において前原を牽制した。しかし、士族の蜂起は熊本の方が早かった。明治九年、神風連ノ乱である。
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
大正12(1923)年、大阪市に生れる。大阪外国語学校蒙古語科卒業。昭和35年、「梟の城」で第42回直木賞受賞。41年、「竜馬がゆく」「国盗り物語」で菊池寛賞受賞。47年、「世に棲む日日」を中心にした作家活動で吉川英治文学賞受賞。51年、日本芸術院恩賜賞受賞。56年、日本芸術院会員。57年、「ひとびとの跫音」で読売文学賞受賞。58年、「歴史小説の革新」についての功績で朝日賞受賞。59年、「街道をゆく“南蛮のみち1”」で日本文学大賞受賞。62年、「ロシアについて」で読売文学賞受賞。63年、「韃靼疾風録」で大仏次郎賞受賞。平成3年、文化功労者。平成5年、文化勲章受賞。平成8(1996)年没
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Die-Go
132
再読。来年の大河ドラマに備えて読む。明治初期に興った「征韓論」から始まり、明治以降最大の内乱「西南戦争」までを描く。不満を抱く士族の勢いは徐々に加速度を増していく。長州では前原一誠を中心として乱を画策する者達がいたが、熊本において「神風連ノ乱」が先を越しておきてしまう。時代がうねりを増していく様が痛みを伴って伝わってくる。★★★★☆2017/12/26
とん大西
100
漸く読了。修業のような読書でした。萩の乱に神風連の乱。征韓論から西南戦争に至るまでに起こりうるべくして起こったカオスというべきか。近代国家への一つの過程なのか。西郷にしてみれば単なる喧騒か、それとも胸に迫る圧力か。でも西郷さん、狩りに出っぱなしで物語に顔を出しやしない( ̄▽ ̄;) 主役不在のまま外堀は徐々に、しかし確実に埋まっていく。…つい、日本人とは何者かと考えてしまう。太政官政府が強行する武士のアイデンティティ喪失。西郷、大久保が荒れる太平洋の真ん中に日本人の精神を投げ入れた感じやよなぁ…。2018/06/09
優希
94
士族は反乱気分を抱えていたのがわかります。政府は長州人集団を潰すことで、権力を握りたかったのかもしれないと思いました。西郷どんは殆ど黙しており、その他の様々な人々を通じて、時代の背景がよくわかります。萩の乱は政府側の勝利しますが、その前に神風連の乱を起こすほど、反目していたようですね。ここから西南戦争への足取りが始まるのでしょうか。2019/01/25
サンダーバード@読メ野鳥の会・怪鳥
88
ようやく6巻、後半戦に突入。しかし話はまだまだ始まらない。沈黙する薩摩をよそに、長州の前原が動き、熊本で乱が始まる。一方、このころの西郷は依然として隠遁生活、意識的に世の中から一切の接触を断っている。はたして彼が何を考えていたのであろうか。西郷はその思想とういう物を文章として残すことはなかったらしい。彼が当時どう思っていたのか?今となっては知るすべもない。2013/04/20
やっちゃん
80
前原が密偵にしてやられるエピソードが印象的。「征韓党、封建党、そして民権党については、じつはみな十把一絡げの不平家なのだ」不平家にとってまだまだ維新は終わっていなかったんですね。しかし久光はブレないなあ。2024/02/21
-
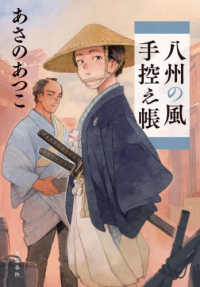
- 和書
- 八州の風手控え帳
-

- 電子書籍
- 偽りの武神【タテヨミ】第19話 pic…