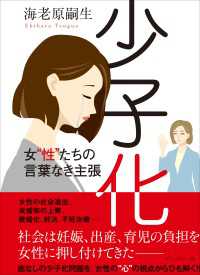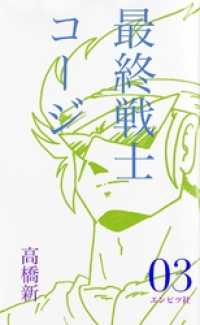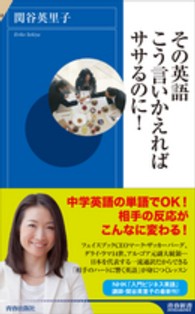内容説明
1955年、共産党第6回全国協議会の決定で山村工作隊は解体されることとなった。私たちはいったい何を信じたらいいのだろうか―「六全協」のあとの虚無感の漂う時代の中で、出会い、別れ、闘争、裏切り、死を経験しながらも懸命に生きる男女を描き、60~70年代の若者のバイブルとなった青春文学の傑作。
著者等紹介
柴田翔[シバタショウ]
昭和10(1935)年東京生まれ。35年東京大学大学院独文科修士課程修了後、ドイツ留学。44年同大学助教授に就任。教授、文学部長を歴任し、平成7年(1995)年退官し、名誉教授。昭和39年「されどわれらが日々―」で第51回芥川賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
380
1964年上半期芥川賞受賞作。全体のスタイル、そこから受ける感慨は鷗外の『舞姫』を想起させる。すなわち、すべてが終ったところからほろ苦く青春が回想される構図が。時間の彼方にあるものは、やはりそれだけでロマネスクである。あるいは、太宰の『晩年』を想わせもする。この小説が執筆された時、作家は29歳であったが、小説内世界においても、また作家自身の諦念においても、若々しさよりは、それを過ぎてしまった感覚が濃密だからだ。そして、六全協の敗北感よりも、一層に個的な中での世代的連帯と共感とを回想しているかのようだ。2013/10/15
kaizen@名古屋de朝活読書会
171
【芥川賞】出てから古本屋に並びはじめた頃購入して何度も読んだ気がする。40年ぶりに読んで見て、記憶以上にしっかりした構成になっている気がした。自分よりは少し上の世代であるので、わからないこともいろいろある。時代の雰囲気をよく描写している。芥川賞作品が現代日本史の勉強によいことが分かる。 2014/02/22
かみぶくろ
114
真正面から生きることに苦悩する、感傷的な青春小説。このひたむきさは本当に眩しく、清々しく、痛々しい。学生運動に身を投じ、破れ、挫折する若者たち。彼らが本当に欲していたのは、革命ではなく空白を満たす「生の実感」だった。心の深いところに蓋をしてトランス状態のお祭り騒ぎ、気付けば御輿は瓦解し、霧が晴れれば空虚がよりくっきりと浮かんでいる。死を選ぶものもいた。それでも彼らはすべてに真剣で、もがきながらも必死に生きようとした。その不器用な純粋さが身に軋む。時代と普遍を両捕りした、180万部のベストセラー芥川賞。2015/07/30
遥かなる想い
108
学生運動の最中に青春期を過ごした先輩たちは、この本をどういう気持ちで読んでいたのだろうかと思う時がある。この小説に登場する人々はなぜか みんなインテリであり、学生運動にかかわり、挫折し、そして潰れていく。 正しいかどうかは別にして、ひたむきに生きた先輩たちの青春がそこには確かにある。
hit4papa
70
幼馴染の男女。それぞれ多感な時期を経、可もなく不可もない相手として婚約をするのですが、一つの古書が二人を隔てていくようになって…、という物語です。半世紀前の作品で、当時の青春小説は政治的な運動と切り離せないのかもしれませんね。確かに時代背景は古いのですが、現代であっても、誰もがふととらわれる虚しさは共感できるでしょう。著者は、些細な出来事が男女の間を引き裂く決定打になるというプロセスを、手紙文を挿入しながら見せてくれます。じっくり読めば、胸に迫るものがあるはずです。陰気な内容なのですが。【芥川賞】2021/11/17