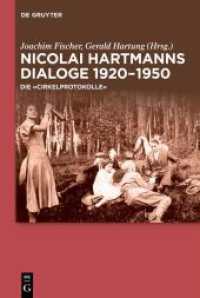内容説明
冷凍技術が発達し、遠方からも安定して鮮度の良い魚が確保できるようになったことで、スーパーなどでは「輸入魚」が幅を利かせるようになった。中国の乱獲による大不漁も重なり、「日本の地魚」は消えつつある。壊れゆく日本の食卓の将来はどうなるのか―。
目次
第1章 見捨てられる日本一の魚
第2章 国産サバが消える?
第3章 サンマが幻の魚になる日
第4章 絶品「大間まぐろ」に不正横行
第5章 ノルウェー産サーモン襲来
第6章 美味しい魚をまずくする「流通」の問題
第7章 ノルウェー漁業との違いと日本の人材育成
第8章 魚大国・ニッポン復活への戦略
著者等紹介
川本大吾[カワモトダイゴ]
1967年、東京都生まれ。専修大学を卒業後、1991年に時事通信社に入社。水産部に配属後、東京・築地市場で市況情報などを配信。水産庁や東京都の市場当局、水産関係団体などを担当。2006~07年には「水産週報」編集長。2010~11年、水産庁の漁業の多角化検討会委員。2014年7月に水産部長に就任した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
54
図書館の新刊コーナーにひっそり佇んでいた本をチョイス☺️著者は、時事通信社の水産部に配属後、東京・築地市場で市況情報などを配信、水産庁や東京都の市場当局などを担当、水産部長の川本大吾氏。日本の漁業・水産業が深刻な状況に置かれている中、日本の「うまい魚」にスポットをあて、世界に誇る日本の魚食を将来につなけたい思いでまとめた一冊。ノルウェー産サーモンの台頭はすでに周知の事実だが、サバも外国産特にノルウェーに持っていかれているとのこと。全日本さば連合会の会長が嘆いているが、全日本さば連合会ってあるんですね😅2025/10/30
よっち
37
深刻な大不漁、超高値、外国産のシェア拡大。日本の漁業・水産業が衰退している理由を取材歴30年以上のさかな記者が明かす一冊。冷凍技術が発達し、遠方からも安定して鮮度の良い魚が確保できるようになったことで輸入魚が幅を利かせる現状。不漁な上に安いイメージが定着して売りにくいイワシ、消費される多くは外国産のサバ、サンマが近年不漁となったいる様々な理由、大間まぐろのブランドを巡る問題、ノルウェー産サーモンの襲来といった様々な問題が挙げられていましたけど、変化してきた食生活もあって立て直すのは簡単な話ではないですね。2024/02/08
金吾
25
漁獲量が落ち込んできているのは、口に入る魚の種類や大きさ、値段から類推できてましたが、読んでみて改めて慄然としました。日本だけでできる話ではないですが、魚資源を復活させていかなければますます魚に関する悪循環が続くのではないかと危惧します。2025/10/21
いとう・しんご
10
読友さんきっかけ。お魚の漁獲量・資源量の問題、輸入魚と流通の問題、漁船上の過酷な労働環境の問題など、興味深いトピックが次々に出てきて楽しめました。ただし、一番大事な最終章の大半を役人の談話が占めていて、竜頭蛇尾の印象もありました。2025/11/07
anken99
6
タイトルに惹かれて購入。近年、あれだけ毎秋に毎日のように食べていたサンマが、ほとんど口にすることもなくなっていたのだが、本書にはそういった日本漁業、そして魚産業の最新事情が大変分かりやすく書かれている。どれも大変面白いトピックばかりなのだが、ノルウェー産サーモンの日本での大成功のストーリーは、これまでまったく知らなかった。たしかに、かつて「サケ」は寿司ネタになかったし、それが今や人気ネタの代表格に。サーモンを安売りすることなく、日本というマーケットに目をつけたノルウェー人の慧眼はすごい。2025/06/09