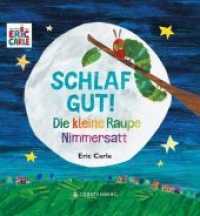内容説明
世界史は年号や用語を暗記する科目のイメージがあるかもしれないが、記憶の断片を繋ぎ直し、ひとつの流れとして把握したとき、歴史の授業はその真価を発揮する。本書は、あなたの知識を大きなストーリーとして繋ぎ直す「大人の学習参考書」である。歴史の流れを押さえれば、現在の世界のニュースが理解できる!
目次
第1章 奴隷・航海・ビートルズ―ヨーロッパ飛躍の秘密 大阪大学
第2章 「パクス・ブリタニカ」との付き合い方 東京大学
第3章 中国とロシアの微妙な関係 東京大学
第4章 中東問題の原点―パレスチナをめぐる世界史 東京外国語大学
第5章 アメリカの世紀とベトナム戦争 東京大学
終章 海が結んだグローバル経済 大阪大学
著者等紹介
津野田興一[ツノダコウイチ]
1965年生まれ。東京都立大学大学院人文科学研究科史学専攻修了。現在、東京都立立川高校で世界史を教える(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
60
大学の論述型入試問題の良問を素材にして、海洋進出に始まるヨーロッパの飛躍、パクス・ブリタニカ、中ロ関係、パレスチナ、アメリカとベトナム戦争などを大づかみに考えていく。本業が高校教員であり、そのレベルの視点であるため、基本的にわかりやすく読みやすい。そして要所はちゃんと押さえてある。昔の暗記型歴史学習をした人には目から鱗かもしれない。高校生が読んでもいいと思うし、若手の歴史教員は必読と思う。いわゆる「低開発の発展」をウォーラーステインに帰したり、p.193のグラフが数値と合ってないなど問題点もあるが。2024/03/17
ta_chanko
15
国立大学の論述問題を通して、世界史を考える。イギリス産業革命の背景には海賊の暗躍と奴隷貿易が。パクス・ブリタニカに組み込まれたインド・トルコ・中国と、対抗したアメリカ・日本。歴史を振り返れば、中・ロ関係は不安定。パレスチナ問題は、ナセルの失脚以降、イスラエル優位に。ブレトン・ウッズ体制を終わらせたベトナム戦争。海が結んだグローバル経済。複雑な現代の国際情勢を読み解く上で、大学の論述問題はとても参考になる。2023/04/01
武井 康則
10
授業ではできない時間の制約上できない世界史の近現代について。人の移動についてが、第一章。後は英国の影響、国境紛争、中東問題、アメリカの繁栄と没落、海の流通について。紙幅の都合上語りが早口になるのは仕方ない。気になったら他の新書で確認しよう。昔読んだ教科書、参考書、新聞を思い出しながら読み進める作業は楽しいが、参考図がいつも次のページにあるのと、写真や図が見にくい。他の新書はもっと鮮明なのに。これが不満。2024/09/05
白いカラス
6
前作「まるわかり世界史」に続く第2弾。今回も大学の入試問題を参考にして歴史を紐解く内容。 あっという間の一読でした。 景気が悪くなり、戦争が勃発して景気が回復する。「ん〜‥」やはり歴史は繰り返すのですね。2022/12/31
gaku7511
3
世界史の近現代史の様々なテーマについて、実際の入試問題をもとに解説していく本。中露関係やパレスチナ問題など、現代にもつながるテーマについて、深掘りして知ることができる。個人的には、岩倉具視使節団とパクスブリタニカをからめた東大の問題をもとにした話が面白かった。2023/01/05