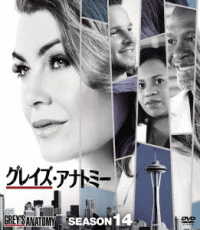内容説明
止められないスマホゲーム、コンビニでつい買うおにぎり、毎晩たしなむ缶チューハイ。日々の何気ない習慣、もしかして「依存症」になりかけているのかも。近年がらりとかわった「依存症」についての知見と対策を、わかりやすく解説。
目次
依存症―この人間的な病
第1部 依存症について知る(依存症とは何か)
第2部 さまざまな依存症(アルコール依存症;ニコチン依存症;薬物依存症;ギャンブル依存症;オンラインゲーム依存症;糖質依存症;性的依存症)
第3部 依存症への対策と治療(薬物依存症への対策―「処罰」から「治療」へ;依存症の治療)
著者等紹介
原田隆之[ハラダタカユキ]
1964年生まれ。一橋大学社会学部卒業。同大学院社会学研究科博士前期課程、カリフォルニア州立大学心理学研究科修士課程修了。東京大学大学院医学系研究科で学位取得、博士(保健学)。法務省、国連薬物犯罪事務所(ウィーン本部)などを経て、筑波大学人間系教授、東京大学客員教授。専門は臨床心理学、犯罪心理学、精神保健学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
99
依存症とは脳の機能障害によるコントロール障害である。また本人の認知のゆがみも関与している。アルコール・ニコチン・薬物・ギャンブル・オンラインゲーム・糖質・性的依存症について、冒頭に嘘と真実を提示して日本の現状を明らかにする。覚醒剤使用者で依存症になるのは20%程度、タバコは80%、アルコールは4%程度。海外ではハーム・リダクションやフィリピンでの著者の体験が印象的だった。日本は公正世界信念が強いと感じる。世界では刑罰より治療なのだ。「禁煙なんて簡単さ。これまで何千回も禁煙したよ」マーク・トゥエイン2021/08/15
ホシ
25
依存症を概説し、アルコール、ニコチン、薬物、ギャンブルなど各種依存症を紹介して最後は著者の依存症に対する治療哲学が披瀝されます。私自身がアルコール依存だったので身につまされながら読みました;;近年、「鬱は心の風邪」という認識が定着した感がありますが、依存症についても、このような認識の転換が必要だと思いました。風邪を引いている人、治った人に対して「ゆっくり休んでね/治って良かったね」と言うように、依存症と闘っている人に対しても同じ事が言えるような社会を構築すべきではないか、そんな事を思いました。2021/07/02
M.O.
24
アルコール、薬物、ゲーム等依存症を解説、最新の取組みを紹介。日本は対応がかなり遅れている。依存性の引き金はネガティブ感情(ストレス)とそれをする仲間がいる事。従って薬物依存などは特にだが刑務所に入れるより治療を優先させるべき。(薬物販売は罰を厳しく) 日本は使用者をつるし上げる事ばかりでオカシイとのこと、確かに。性犯罪は認知のゆがみが大きいため修正が必要。子供を持つ親としてはゲーム依存は頭が痛い。久里浜医療センターの様な支援先が増えるといいと思う。まだまだ少なすぎる。考えさせられる本だった。2021/09/20
テツ
16
脳の機能障害と認知の歪み。多種多様な刺激物に囲まれた現代社会に生きるぼくたちは容易に依存症に陥る。本来快楽とは生きるために不可欠な行動に対して脳から与えられるご褒美であった筈なのに(食事、睡眠、セックス等々。きもちよくなければ誰もやらずに種が滅びてしまう)いつしか快楽を得ることだけを目的として、脳がそれを与えやすい何かをこさえて、それにハマり依存するという本末転倒さに陥ってしまっている。何事もまずメカニズムを知ることだよな。知識として依存症を知っておくことはハマる前のブレーキになる。2023/02/26
jinya tate
13
20年前と比べて、依存症の捉え方や治療のの方法も、格段の進化を遂げていると感じる。変わらないのは行政や世間の懲罰的な態度だ。見せしめということだろうか。 懲罰だけでは依存症は克服できない。治療はもちろん、支援が必要だ。依存症の患者を幸せにできるような寛容さが日本には欠如しているのではないか。2023/05/10
-

- DVD
- 一獲千金を夢みる男
-

- 和書
- 例題で学ぶ符号理論入門