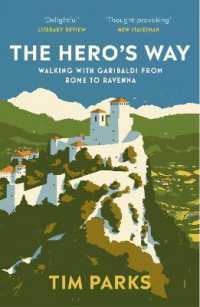内容説明
女性ノンフィクション作家の草分けとして知られる著者。昭和の戦争や重大事件を扱った重厚な作品から、着物について書かれたエッセイ、友人との交遊などを描いた軽妙な作品まで。その魅力を余すことなく収録した「澤地久枝入門」に最適の一冊!
目次
序 その仕事を貫くもの
1 わたしの満洲―戦前から戦中を過ごして
2 棄民となった日々―敗戦から引揚げ
3 異郷日本の戦後―わが青春は苦く切なく
4 もの書きになってから―出会ったひと・考えたこと
5 心の海にある記憶―静かに半生をふりかえる
6 向田邦子さん―生き続ける思い出
著者等紹介
澤地久枝[サワチヒサエ]
1930年生まれ。ノンフィクション作家。東京に生まれその後、家族と共に満洲に渡る。1949年中央公論社に入社。在社中に早稲田大学第二文学部を卒業。退社後、五味川純平氏の助手となり『戦争と人間』の脚注などを担当する。1972年『妻たちの二・二六事件』(中公文庫)で作家活動に入る。1986年、『記録ミッドウェー海戦』(小社刊)で不明だった日米の戦死者3419名を掘り起こした功績により菊池寛賞受賞。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
66
戦争体験、人生における箴言と、自分の卑小さを感じさせるような文章の数々だった。この年代の方々が日本からいなくなってしまうことを、私は心から恐れる。2019/09/29
さきん
25
満州からの引き上げ経験がその後の行動指針に大きく影響していると思われる。よって、日本という国家を常に疑っている。戦後知識人の典型といった感。2020/12/30
かふ
16
澤地久枝入門アンソロジー。文春の編集者が澤地久枝の本からの言葉をまとめたもので、澤地久枝が作家としてやっていくまでの道のりやその過程で出会った様々な思い出を語るような本。昭和を知る世代というより、満州帰国者だったのが彼女の原点だった。そのときの棄民(難民)の苦労話は、現代の戦争にもつながる話であり、戦争を知らない世代には、日本でもそうした歴史があるのだと証言する。それらは歴史の事実として隠されてしまうものであり、ノンフィクションライターとして、澤地久枝が関わってきた問題はそうした問題でもあったのだ。2024/01/24
雨巫女。
13
《私-図書館》学生時代はまった作家さん。向田邦子さんと、友達だったんですね。2021/04/12
ツキノ
8
これまで出版された本、インタビュー、対談などからの抜き書きで「時代の声を刻み続けた約50年にわたる仕事を一冊に凝縮」とのことだけれど、澤地久枝さんの一代記にもなっている。読み応えあり。二十代からのつきあいだった向田邦子さんについての記述に一章を割いている。新書という形態もよかった。2020/04/07
-
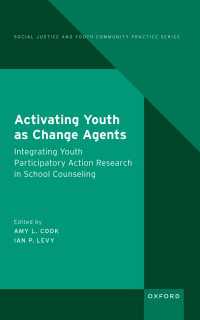
- 洋書電子書籍
- Activating Youth as…