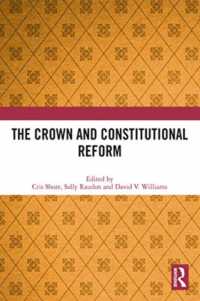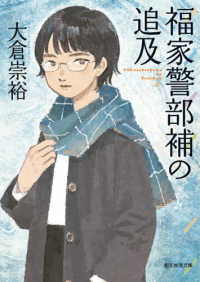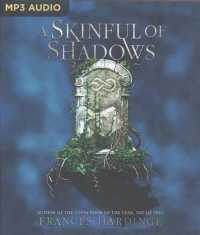出版社内容情報
文明開化の明治の闇の部分が「廃仏毀釈」だ。寺院、仏像の破壊から、僧侶の殺害、暴動まで、文化財、歴史の破壊はなぜ起きたのか?興福寺阿修羅像、五重塔も消滅の危機にあった!
文明開化の明治にも光と影がある。その影の部分を象徴するのが「廃仏毀釈」である。
もともとは神仏習合状態にあった神社と寺院、神と仏を分離する政策だったのだが、
寺院、仏像などの破壊から、暴動にエスカレート。完全に仏教を殲滅してしまった地域もあった。
寺に保管されていた記録、史料などが焼かれたことで、その地域の「歴史」も消えてしまったケースすらある。
日本史上でも例が少ない大規模な宗教への攻撃、文化財の破壊はなぜ行なわれたのか?
話題作『寺院消滅』などを著し、自らも僧侶である著者が、京都、奈良、鹿児島、宮崎、長野、岐阜、伊勢、東京など日本各地に足を運び、廃仏毀釈の実態に迫った近代史ルポ。百五十年のときを経て、歴史が甦る!
【こんな事実が!】
焚き火にされた天平の仏像
仏具が京都・四条大橋に
比叡山から上がった”火の手”
廃仏のルーツは水戸黄門?
すべての寺が消えた東白川村
青山霊園、谷中霊園は神仏分離によって造られた
天皇家の菩提寺も消滅 ほか
鵜飼 秀徳[ウカイ ヒデノリ]
著・文・その他
内容説明
明治百五十年でも語られない闇の部分、それが廃仏毀釈だ。神社と寺院を分離する政策が、なぜ史上稀な宗教攻撃、文化財破壊にエスカレートしたのか?日本各地に足を運び、埋もれた歴史を掘り起こす近代史ルポルタージュ。
目次
第1章 廃仏毀釈のはじまり―比叡山、水戸
第2章 維新リーダー藩の明暗―薩摩、長州
第3章 忖度による廃仏―宮崎
第4章 新政府への必死のアピール―松本、苗木
第5章 閉鎖された島での狂乱―隠岐、佐渡
第6章 伊勢神宮と仏教の関係―伊勢
第7章 新首都の神仏分離―東京
第8章 破壊された古都―奈良、京都
著者等紹介
鵜飼秀徳[ウカイヒデノリ]
ジャーナリスト、浄土宗正覚寺副住職。1974年京都市右京区生まれ。成城大学文芸学部卒業。報知新聞社、日経BP社を経て、2018年1月に独立。一方、僧侶としての顔も持つ。一般社団法人「良いお寺研究会」代表理事。東京農業大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ろくせい@やまもとかねよし
佐島楓
さつき
1959のコールマン
ネギっ子gen
-

- DVD
- ミート・ザ・ペアレンツ
-
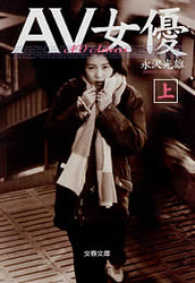
- 電子書籍
- AV女優(上) 文春文庫