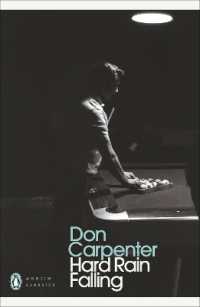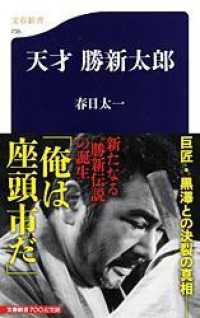出版社内容情報
あまた発表してきた映画評から著者自らが選んだ「ディレクターズ・カット」。文芸大作からおバカ映画まで、時空を超えて自在に展開。
内容説明
「映画は、映画について語られることを欲望しているジャンルである」が持論の著者が、長年、書きためた映画評の中から自ら厳選。画期的な小津安二郎論10本を含む187本。
目次
第1章 うほほいシネクラブ(『2046』;『きみに読む物語』;『ミリオンダラー・ベイビー』 ほか)
第2章 街場の映画論(ラス・メイヤーとクリント・イーストウッド;『お早よう』再見;『冬のソナタ』と複式夢幻能 ほか)
第3章 小津安二郎断想(通過儀礼としての小津映画;大人の教科書;食卓の儀礼 ほか)
第4章 おとぼけ映画批評(『アニマル・ハウス』&『ブルース・ブラザース』;『アナコンダ』;『ゲーム』 ほか)
著者等紹介
内田樹[ウチダタツル]
1950年東京生まれ。東京大学文学部仏文科卒。東京都立大学大学院博士課程中退。2011年3月、神戸女学院大学大学院文学研究科教授を退職。現在は同大学名誉教授。専門はフランス現代思想、映画記号論、武道論。2007年『私家版・ユダヤ文化論』で第6回小林秀雄賞を受賞。『日本辺境論』で新書大賞2010を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
踊る猫
24
日記ですね、これは。ウェブに掲載した短めの映画評/レヴューの集大成だが、活字メディアを通したハードコアなものではないため、良く言えば柔軟なアイデアがそのままレアに形となっている。悪く言えば単なる思いつき。だが、内田先生の思いつきはなかなか侮れない。高橋源一郎のようにどんな映画も(ゴダール、小津からタランティーノまで)フラットに吸収しそれをウチダ節でぶった斬っていく。その手つきはある程度のアクチュアリティはあるが、この言説には何処まで責任を取る気なんだろうと訝しく感じさせられてしまうのも確かで、評価が難しい2019/12/09
かっぱ
23
新書だけど400ページ近くもあって持ち歩くのに不便(笑)。やっと読み終えた。いろいろ観てはりますなぁ。なぜか、これを読んで観たくなったのが「冬ソナ」と「小津映画」でした。泣くんですね、このお方。冬ソナの項で男女の出会いについて書かれたところが気に入りました。「はじめて出会ったときに私が他ならぬその人を久しく『失っていた』ことに気づくような恋、それが『宿命的な恋』なのである。はじめての出会いが眩暈のするような『既視感』に満たされて経験されるような出会い。私がこの人にこれほど惹きつけられるのは、私がその人を一2012/01/10
Nobu A
21
敬愛してやまない内田樹先生だが、残念ながら本著はいただけない。そもそも対象は誰?基本も押さえず、鑑賞映画に関する雑感を垂れ流し。制作・上映年の記載なし。監督や出演者の記載があったりなかったり。英語と日本語表記もバラバラ。今時、単一ジャンルの映画など皆無。「スターシップ・トゥルーパーズ」が青春映画?SF戦争映画だろう。紹介映画9割程は鑑賞済み。近年の年間上映本数はおよそ8百。映画評論家はその内少なくとも5百は鑑賞。全然足りないよ、内田先生。申し訳ないが、映画評論は専門家に譲りましょう。後半斜め読み読了。 2022/06/13
たらお
21
映画をたくさん観てきている人の文章である。監督の過去の作品の傾向についても論じつつ、映画の解析をしている。でも、そんな説明より主観が大いに入っている紹介文が好き。黒澤映画「乱」で「新劇」感を出した仲代達也の演技についての嫌いさが如実に表れているおかしさや、タランティーノとディビット・リンチが好きなところにも親近感が湧く。タルコフスキーの「ストーカー」気になっていたけどこの評を見るとまだ手を出せないなとか、「仁義なき戦い」借りてみようかなとか、リンチの「マルホランド・ドライブ」もう一回観ようかなとか思った。2016/05/05
Yusukesanta
18
今日はデヴィッド・リンチの誕生日ということで、以前、読んで感動した内田先生のマルホランドドライブ評だけを、また読む。野心的なフィルムメーカーは、必ずいつか「映画についての映画」を撮る。ゴダール「気狂いピエロ」タランティーノ「パルプフィクション」...とか。でもってリンチの映画も例外でなく、どころか、いままで徹底して積み上げてきたリアリズムを、映画の中で否定するようなことをして、フィクションを「難民化」させる。映画は唐突に終わる。観客はどうしていいかわからない。「難民化」という言い方はおもしろい。ううむ。2016/01/20