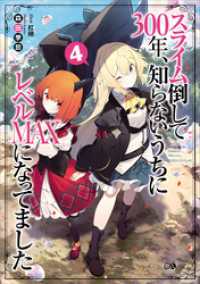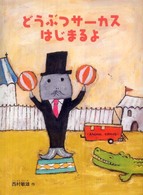内容説明
刀剣を研磨、鑑賞し、宝物として残す文化は日本独特のもの。名刀は権威の象徴として将軍、大名に受け継がれて現代に伝えられ、皇室でも大きな役割を果す。日本刀の奥深い世界に誘う。
目次
武士の魂というが
荘厳なる日本刀のかたち
刀剣目利
刀鍛冶の名前
正宗出現
鉾と槍と薙刀
刀狩りと新刀
刀装
長曽祢虎徹
奈良刀と切れない刀
幕末と明治以降の刀剣
著者等紹介
小笠原信夫[オガサワラノブオ]
1939年生まれ。早稲田大学卒業。日本美術刀剣保存協会を経て、東京国立博物館勤務。刀剣室長、工芸課長等を歴任。東京国立博物館名誉館員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
ほりちゃんの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みや
28
精神的支柱としての日本刀の変遷を教える学術書。真面目で堅い文章と古い文献の膨大な引用は非常に取っつきにくい。この本に書かれた内容を全て理解するところまでには、まだ到底至ってなかった。一歩踏み込むだけで俄然難しくなるから、やはり日本刀は面白い。代銘や二つ銘、襲名制度による鑑定の難しさや刀工・刀派の複雑さに、興味が更に増した。武器の良し悪しの判断だけをする職業があったのは日本だけではないか、とのこと。日本と日本刀だけにとらわれず、世界各地各時代での武器の捉えられ方や価値観など、もっと視野を広げて見ていきたい。2019/03/10
河童
4
実際に日本刀を見て説明を受けたり、ネットで一つ一つ検索して確かめない限りこの本の専門用語がなにを意味するのか具体的な理解が進まないでしょう。日本刀に関する知識のない私には難しい。しかし興味をもって追究すれば面白い分野なのだろうと思う。2018/09/28
にゃん吉
3
日本刀に若干の興味があって、入門書的な本かと思って手に取りましたが、持て余してしまいました。専門用語や人名が、あまり解説されることもなく、ぽんぽんと出てきたり、テーマが掲げられてはいながらも、該博な知識が徒然なるままに記述されているような書きぶりで、何の話だか途中で分からなくなったりと、苦戦。引用されている文献が多いのは、よいなと思いましたが、「梁塵秘抄」「武家の女性」「幕末百話」等、自分が読んだことがある文献の引用箇所について全然記憶になく、自分に苦笑した次第でした。 2020/08/20
rbyawa
3
f047、ジャンル2冊め、大雑把に刀匠の系統の本ではないかと思うものの、個々人の系統や説明の前に「記述の混乱」や真贋判定みたいな話になっちゃったのはちょっと新書としては難しかったかなぁ、というところか。むしろ巻末にあった名刀匠一覧は先に読ませておいたほうがマシだったんじゃなかろうか、端的でわかりやすいしあれ。存在していないとまで言い出される正宗、実践刀として名高い虎徹なんかの話は面白かったかなぁ、というか粟田口やら三条宗近が前提知識として求められていたような気もする(説明にいきなり出てきた)、いいけどさw2015/03/03
さとちゃん
2
前々から興味ある分野の書籍でしたが、基礎知識がなさ過ぎて半分も理解できなかったように思います。3年後くらいには、頷きながら読めるようになりたいものです。2016/05/24