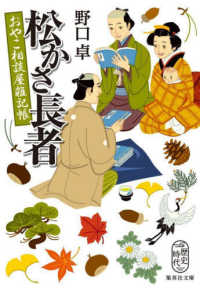内容説明
小学校での英語必修が目前に。同時通訳者として本物の英語力を知るからこそ、あえて問う。
目次
第1章 「早ければ早いほど」幻想を打ち砕く!
第2章 「親の過剰な期待」が英語必修化への道を開いた
第3章 誰が英語を教えるのか
第4章 日本の英語教育はどうあるべきか
著者等紹介
鳥飼玖美子[トリカイクミコ]
東京生まれ。上智大学外国語学部卒業。コロンビア大学大学院修士課程修了。国際会議やテレビなどの同時通訳者を経て、立教大学教授(経営学部、大学院異文化コミュニケーション研究科)。国土交通省交通政策審議会委員、日本コングレス・コンベンション・ビューロー会長、国立国語研究所評議員、日本通訳学会会長。専門は英語教育、英語コミュニケーション論、通訳翻訳論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
271
英語教育が大事だとか色々やかましい議論が続いているが、本書は英語を教えることについての問題点が挙げられておりよくわかった。私も中学の時、英語教育は必要かどうかでみんな英語教育が必要だとか言ってる中、一人だけ英語教育は必要ないとの論陣を張った覚えがある。それほどみんななんとなく英語が必要とか思っていて驚いた。2016/07/02
kinkin
99
私は小学校の英語教育はするなとは言えないが本書にも書かれているようにまずは母語が確立してからのほうが良いと思う。教える側も教え方や能力にも差がある、いやありすぎるのではないか。確かに幼児から教えて末はバイリンガルになったら親の面子も立つもの。しかしほんとうに英語能力を高めるのはモチベーション。今後はプログラミングも教えるそうだけど小学校からあれもこれも詰め込みすぎではないか。ゆとり教育を唱えているわけではなく国語の基礎をしっかりやってから何事も教えないと意味がわからない英語やプログラムができてくると思う。2019/05/07
Miyoshi Hirotaka
45
外国語の能力が母語の能力を超えることはない。8割が限界だといわれている。外国語の上達は、母語での読み書き、思考、表現の能力に比例する。早く始めて「習うより慣れろ」ではなく、「慣れるまで習え」なのである。市場拡大を狙う業界と親の過剰な期待が早いほどいいという根拠のない俗説を生み、小学校での英語必修化を後押ししている。子供に必要なものは、惜しみない愛情と豊かな母語。母語での思考と表現ができ、他者とのコミュニケーションが取れれば、その後の外国語習得は動機次第。しかも、英語だけがすべてではない、世界は広いのだ。2016/03/16
ヴェネツィア
31
小学校での英語教育の是非を論じたもの。著者は、少なくても今のあり方には反対の立場。導入には産業界からの要請と、親の英語コンプレックスが文部科学省の思惑と一致(あるいは後押し)したと分析する。ATL(英語アシスタント)の実態も紹介しているが、あれでは税金の無駄使いだ。TOEICが日本だけのものというのも初めて知った。私も、小学校での英語教育は無駄どころか、マイナスの方が多いと思っているし、筆者の主張―中学校の英語教育の抜本的改革―に全面的に賛成だ。2012/06/16
ふろんた2.0
29
10年前の本なので、あれこれ意見するつもりはないけど、国の方針というよりも保護者の要望のほうが色濃いようだ。英語でコミュニケーションが取れることが目的にあっても、受験科目に英語がある、準備は早いに越したことがない、周囲が英語教室に通いだした、じゃあうちも遅れをとるから勉強させなきゃ、みたいな狭い目的にいつの間にかすり替わっているんだろうな。2016/07/16