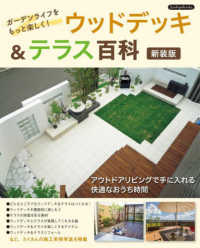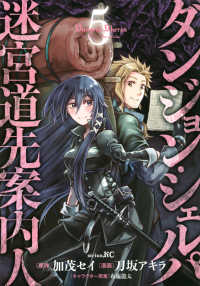内容説明
桜と深いかかわりを持つ日本文化。桜がどのように文学上のテーマ、モチーフを形づくってきたかを、古事記や日本書紀、万葉集から現代の渡辺淳一まで丹念にたどりながら、日本人の心や文化に、梅や菊とも異なる、大きな影響を与えるに至った経緯を解き明かす。紫式部、西行、世阿弥、豊臣秀吉、松尾芭蕉、本居宣長、与謝野晶子、ハーン、萩原朔太郎、そして梶井基次郎をへて、谷崎潤一郎、水上勉、中村真一郎らへと継承され、変容した豊饒な桜の文学絵巻。
目次
さくら讃歌―序にかえて
古代に咲く=飛鳥・奈良時代
王朝絵巻のさくら=平安時代(前)
薄明に咲く=平安時代(後)
さくら美の完成者たち=鎌倉時代
さくらのドラマツルギー=室町時代
聖から俗へ=桃山時代
新しいさくら文化の開花=江戸時代
文明開化とさくら=明治時代
さくらの歌びとたち=大正時代〔ほか〕
著者等紹介
小川和佑[オガワカズスケ]
文芸評論家(東京電機大学講師・元明治大学文学部兼任講師)。日本文芸家協会・日本ペンクラブ会員。1930年、東京生まれ。明治大学卒
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まつこ
20
季節に合わせて読んでみたが、桜についてとても専門的だったので難しかった。桜の種類って200種類もあったなんて。巻末に種類別の表や桜作品の文献も載っていてよかった。 古代~中世の桜とは貴族のものだった。そして桜は散ってもまた咲くから、その時代では生命の蘇りの象徴であったという。それが都市市民にも桜を愛でる文化が定着するようになってから、儚く散る桜を戦争の象徴としてしまうようになった。確かに昔と今では観ていた桜も違うから。でもやっと昔に戻って、蘇りとしての桜を愛でるときが来たように思う。2013/04/02
双海(ふたみ)
10
興味深い本であるが、少々癖がある?とくに本居宣長への批判が印象に残る。宣長は「国学を振りかざしてすっかり桜観を歪めた元凶」であるとし、「宣長のさくらなんぞは見たくもない」と言い切る。さらに宣長は「思想家であっても、詩人ではなかった」と言う。歌人としては駄目だったということだろう。この頁以降、私は読み進める気がどうも失せてしまった。2013/12/03
1.3manen
4
桜をモチーフとした古代から現代に至るまで、日本人にとっての桜をモチーフとして、文学作品を通じて、日本人の精神性を描写しようとした逸品。各時代の特徴では、秋に咲く桜が『日本書紀』に見え(16ページ)、散りゆくさくらを描く『古今和歌集』(49ページ)、シダレザクラの西行桜(87ページ)、島崎藤村少年時代の江戸川の桜堤の詩句(183ページ)、ベルツの日記にもある花見(186ページ)、など、多くの文人が桜から受けた作風は計り知れないのだ。桜は日本人の根幹を司る。あの短期間で散る儚さと優美さ。蝉の鳴き声と重なる。2012/07/22
にご
3
○亡祖父の本2。桜の花が咲いた頃に読み始めて、花が散る前に読み終わろうと思っていたのに、読み辛くて葉桜になった頃にようやく読み終わった。古代から現代まで日本文学における桜のイメージの変遷を丁寧に追った本。桜が日本人にとって特別なものになったのは、人の身近にあり続けることで各人に桜と共にあった記憶が残ったからだし、(国粋主義のようなものもあったとはいえ)イメージを付与されたから。そして、何よりも美しかったから。それにしても本居宣長のこと嫌いすぎだろう。2016/04/13
tamadon
2
「桜ばな いのち一ぱいに 咲くからに 生命をかけて わが眺めたり」(岡本かの子)という、満開の花から触発された生命感あふれる歌もあれば、「遠く桜のはなは酢(す)え 桜のはなの酢えた匂ひはうつたうしい」(萩原朔太郎)という、桜の花の美しさから逆に作者の陰鬱がもたらされた詩など、さまざまな引用が並ぶ。2010/03/22
-
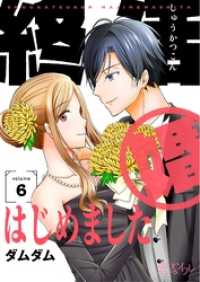
- 電子書籍
- 終活婚はじめました 6 恋するソワレ
-

- 電子書籍
- シーク様とハーレムで。(6)