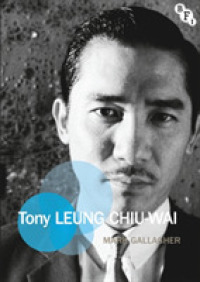内容説明
生まれてから一度も俳句を作ったことのない人はいないはずだ。「朝起きて/顔を洗って/歯をみがく」などと五・七・五を並べ、「季語がないじゃないか」と先生に言われた国語の授業の思い出は、みんなが持っている。ところが、大人になるとほとんどの人は俳句から遠ざかってしまう。そして、俳句を作るのは「結社」という家元制の特殊な世界に集まる人たちだけ。でも、俳句はそんなものじゃない。たった十七文字の奥の深い楽しみに、もう一度チャレンジしよう。
目次
第1章 俳句の出自の芭蕉(同時代人としての松尾芭蕉;俳句と俳諧 ほか)
第2章 子規の俳句革新(駄句の山などなにするものぞ;ターゲットは月並俳句 ほか)
第3章 経営者・虚子の功罪(歪められた子規像;忘れちゃいけない碧梧桐 ほか)
第4章 秋桜子、誓子の影響(ホトトギス黄金時代;秋桜子の不満 ほか)
第5章 新興俳句運動(窓秋の新しさ;波郷と楸邨 ほか)
著者等紹介
中村裕[ナカムラユタカ]
1948年、北海道生まれ。フリーランスの編集者、ライターとして各種雑誌、書籍の制作にたずさわる。1988年から2001年まで俳人の三橋敏雄に師事、句集に『石』(鞦韆堂)がある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
オールド・ボリシェビク
1
著者は北海道出身の編集者らしいという。俳句は三橋敏雄に師事した。芭蕉から始まり、子規や虚子、そして新興俳句運動までの通史を追うが、確かに「やつあたり」気味に、虚子の商業主義などを糾弾して面白い。渡辺白泉に対する飯田龍太の低評価など、「へえ」と思わせる指摘で読ませてくれた。俳句の歴史にもいろいろな盲点があるもんだ。2022/06/24
Y.T
0
☆☆★2016/03/13
shouchann
0
入門書のつもりで読み始めたのだが、入門書ではなく、俳句の世界の歴史書であった。戦前の振興俳句運動など知らなかったので、興味深く読めた。2015/11/12
かわのふゆき
0
入門とするにはアクが強い。2011/06/17
ヘビメタ小僧
0
俳句は数年前全くの独学でやってみたが、一人では続かなかった。そこで気になって読んでみた本だが、筆者も書いてるように入門書ではない。俳句の流れを主観的視点を強めに書かれた書籍。治安維持法での弾圧は初めて知ったし、自由律の位置も大体分かった。ま、作品を創ることとは直接関係は無いかもしれないが押さえておいていいし、何事も「歴史は勝者の都合よいように」記されるものだから…2009/07/22
-

- 電子書籍
- ふたりの千佳~完璧な彼女には秘密があり…