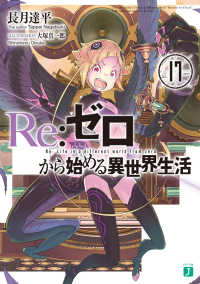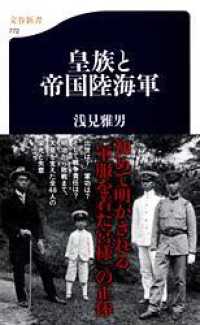内容説明
日露戦争の勝利に驕った軍部は精神主義に固執し近代化を怠ったという俗説がある。しかし、陸海軍上層部にも軍の状況に危機感を抱く軍人は多く、国防方針策定の真剣な努力も重ねられた。しかし、それでも日本は大東亜戦争で惨敗した。果してその原因はどこにあったのか。大正期以降の日本軍の弱点は、まさに日本近代社会の弱点そのものだった。
目次
第1章 日露戦争後の国防
第2章 第一次大戦末期の国防
第3章 大正末期の国防
第4章 昭和初期の国防
第5章 昭和一〇年代初めの国防
第6章 大東亜戦争前の国策と国防
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
父帰る
5
著者自身が述べているように、本書は軍事を中心に大東亜戦争に至る経過を追った書である。その意味では、極めて類例の少ない本である。国防思想を時系列的に知るには格好な書だ。ただ著者が訴えたかったのは、単なる国防思想の変遷ではない。その変遷から、勝算も戦争終結の目算もないまま開戦することになる過程を抉り出している。陸海軍が自分たちの組織的要求を優先し、国家全体の意思として日本の安全をないがしろにした。その原因を元老なき後の国家的見地に立って大局から判断できる指導者の欠如に求めている。アメリカにはルーズベルト大統領2014/10/29
だっしゅ
2
昭和11年の「国防国策大綱」に関心があって読むことに。元自衛官の方が書かれた本でワーディングにはやや癖があるものの、帝国国防方針の変遷や策定にあたっての議論が丁寧に解説されていてわかりやすい。よく言われることではあるけれど、資源・生産ライン・予算等に限りがある中で陸海軍の組織的利益が国防方針の統一と競合したこと、分権的な国家体制の中でトップレベルの調整が機能しなかったこと等々。組織に縛られがちな官僚からボトムアップで戦略を立案することは可能なのか(戦前の日本に特有なのか、それなりに一般性があるのか)。2020/10/04
Naota_t
1
★3.3/何より情報量がすごいので勉強になった、かつ若干評価を上げたが、その分読むのが大変。事実の羅列が多く、著者の提案等はあまりなかったのが少し残念。要するに、20世紀前半には国のリーダーがいなかったのだ。(天皇、)陸軍、海軍、空軍で誰も責任を取る体制でなく、自己組織優先のエゴイズム、予算の取り合い、それぞれ軍内でも意見もバラバラ、縦割り構造の典型だった。国家戦略や、資源のない戦争に勝算・目算もなく、ただ総花的に前にだけ進む状況。確かにこのような状況では、悲しいが南京事件が起こるのは納得できた。2022/05/20
みずい
1
日露戦争後20年近く国防方針が迷走した挙句、敗戦した日本の右往左往を描いた一冊。秀才軍事官僚が、結局のところ軍備整備と高級ポストの確保しか考えてなかった無能揃いだったのがよく分かる。テーマとはズレるが「満州を侵略しても反応が鈍かった英米が、上海事変が起きた瞬間に危機感を抱いたのは、上海にネームバリューがあり彼らが良く知ってる都市だったから」というのは初めて見た視点で面白かった。現代でも、尖閣諸島と沖縄の知名度の違いで似たようなことが起こりそうっすな。2016/01/30
ムカルナス
1
日露戦争後の軍事面の状況推移を詳細に記した本。陸海軍ともに組織の拡大のために仮想敵国との戦争に備えての軍備予算を主張。そこには世界情勢、国家戦略といった視点が欠ける。その軍部を抑えて国家戦略に見合った軍事行動させる元老はおらず政治、外交、軍部の意見が統一されないままズルズルと日中戦争、太平洋戦争へと引きずり込まれていく。戦前の日本は独裁侵略国家と思われているのかもしれないが本書を読む限り リーダー(独裁者)不在で国家戦略がないまま欧米列強に見合った国力をつけることのみを目標に汲々している姿しか見出せない。2014/10/14