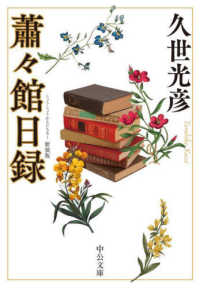内容説明
なぜ大衆登山は現在の隆盛をみたのか―。象徴的にいえば、コンビニと高速道路網の普及がそれを可能にした。これまで山書分野で語られることの少なかった山小屋、登山道、林道など、登山の舞台裏を紹介しながら、日本百名山登山ブームの実態に迫る。意外に知らない話、例えば、遭難救助ヘリはいくらか、黒部峡谷の歩道は誰が管理しているのか、なぜ上高地はマイカー規制になったのか、アルプス展望台のお薦めは、等をデータと併せて満載している。
目次
第1章 山小屋について
第2章 百名山登山をめぐって
第3章 登山者層について
第4章 登山道について
第5章 電源開発と林道について
第6章 山の環境保全について
第7章 もう一つの登山の楽しみ
著者等紹介
菊地俊朗[キクチトシロウ]
1935年、東京生まれ。早稲田大学政経学部卒業。信濃毎日新聞入社。社会部長、常務取締役松本本社代表等を歴任、現在、監査役。記者時代より山岳遭難、山岳環境問題を追求。この間、64年、長野県山岳連盟を中心とするヒマラヤ・ギャチュンカン(七九二二メートル)登山隊に隊員として参加。その遠征報道で日本新聞協会賞(編集部門)を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
246
山の社会学という割に実際は最近の登山状況を述べられていた。古い本だけど近年はどんどん便利になってることを知った。一度山登りしてみるのもいいなと思った。2016/06/25
いっしー
19
トレッキングをするにあたり、手始めに手に取った一冊。社会学というよりは、著者が登ったことのある山々についての思い、感想を集めた本と言ったところか。山好きの方は遠くの地域まで足を伸ばされるようだが、地元でも登ったことがない山にも言及されていて、これから登るに当たり予備知識として参考になった。あとは、個人的には実践あるのみか…2016/09/04
LaVieHeart
7
以前、山の遭難のネット記事に「勝手に他人の土地に入り込んで云々」という非難コメントを見た。有名な山は大体国有林なんでは?と思いながら見ていたのだが、「そういえば登山道は山小屋のご主人が整備している話を良く聞くけれど、山が国の物だとしたら実際誰が管理しているのか?」と疑問に思っていた。その辺の事についても、事故の際の責任問題や金銭的問題から国が地方に擦り付けようとしている姿が見えてきた。そのくせ山小屋には地代として利益の一部を上納させようとしてるから胸糞悪い。四半世紀前の本だが、今も変わってないのだろうか?2024/05/24
まさげ
6
時代とともに登山の形態、山小屋の形態も変化していくことを実感した。30年前に訪れ.高天原の秘湯は変わらずにいてもらいたいと思う。 2017/06/06
dongame6
4
社会学と言われると社会学って何?となってしまうが、2001年当時で数十年の登山経験を持っていた著者によって書かれたこの本は、十数年前の日本の登山の環境について登山道の整備や山小屋の営業、医療や救助、登山をする側と言うよりは登山者を受け入れる側の視点で書かれており、観光登山の長いブームがどういった問題を内包しているか、そして受け入れ側はどうそれに対応してきたかなどを考えさせられる一冊だった。2019/08/07