内容説明
伝説の俳人/書家の画期的な評伝。
目次
俳句第二芸術論―赤い椿白い椿と落ちにけり
子規と碧梧桐―師を追うて霧晴るゝ大河渡らばや
三千里の旅へ―鳥渡る博物館の林かな
新傾向俳句の誕生―思はずもヒヨコ生れぬ冬薔薇
龍眠帖と龍眠会―鮎活けて朝見んを又た灯ともしぬ
碧梧桐と虚子―虚子といふ友ありけりや冬瓜汁
無中心論の展開―相撲乗せし便船のなど時化となり
登山家・碧梧桐―立山は手届く爪殺ぎの雪
『八年間』の麗姿―ローマの花ミモーザの花其花を手に
関東大震災の記録―松葉牡丹のむき出しな茎がよれて倒れて
新切字の探索―汐のよい船脚を瀬戸の鴎は鴎づれ
ルビ付俳句の意義―虎猫友猫なうて来る鼻声鼻黒が痩せて腰骨
碧梧桐死す―金襴帯かゝやくをあやに解きつ巻き巻き解きつ
著者等紹介
石川九楊[イシカワキュウヨウ]
1945年福井県生まれ。京都大学法学部卒業。京都精華大学教授、文字文明研究所所長を経て、同大客員教授。1990年発刊の『書の終焉 近代書史論』(同朋舎出版)でサントリー学芸賞を受賞。1992年『筆蝕の構造 書くことの現象学』(筑摩房)を上梓、「筆蝕」による書の読み解きの理論を確立。2002年『日本書史』(名古屋大学出版会)で毎日出版文化賞、2009年『近代書史』(名古屋大学出版会)で大佛次郎賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
茶幸才斎
6
正岡子規の歿後、新傾向俳句を生み、更に徹底した写生主義による無中心論に進み、その後も五・七・五の定型音数律や季題からの離脱、多様な切字の使用、果てはルビ付き俳句など、高浜虚子が率いる旧態依然の俳壇主流派の理解の及ばぬ俳句作法の飽くなき追求、開発に挑んだ河東碧梧桐の業績を解説し評価した力作である。書家である筆者が、各時期に碧梧桐の輝毫した俳句の書体から解き明かす彼の思想や立ち現われる句の味わいが、非常に面白い。表紙の碧梧桐の直筆題字が、息子の書く下手くそな字に似てるなと思って買った本だが、大変な収穫だった。2023/03/17
むっち
1
高濱虚子の名前しか知らなかった程度の読者の私には読み進めるのは骨の折れるものだったが、第一と第二章ははっとする指摘があり読み進めるうちに、確かに無視されるべきではない仕事をしている俳人・書家(表現の求道者とでも呼ぶ方がいいのかもしれない)人物の人生が浮かび上がる。日本語が漢字、ひらがな、カタカナの三つからなる混合語という指摘はこれまで意識してこなかった日本文化を読み解く視点かもしれないと考えた。俳句は芭蕉のものというのもなるほど。 2020/08/13
かみむら
1
書家による河東碧梧桐論。碧梧桐の書や著作等を通し、碧梧桐が目指した俳句の表現について解説しています。 書の書きぶりから句やあるいは書き手を捉えるあたりはさすが書家と云うべきでしょうか。 全体としては、碧梧桐がどう俳句と向き合っていったのかを詳しく解説していてなかなかに興味深い内容でした。内容の濃さに碧梧桐愛を感じます。 が、一方で著者は虚子の事がよっぽど気に食わないのか、虚子に対してかなり辛辣で、最初は苦笑しながら読んでいたのが次第に辟易してきて、しまいにはどうでもよくなってしまった部分もあります。2019/10/23
-

- 電子書籍
- 身代わり妻は悪魔の囁きにかき乱される【…
-
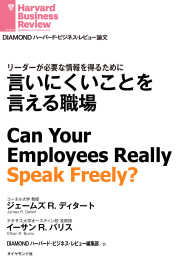
- 電子書籍
- 言いにくいことを言える職場 DIAMO…







