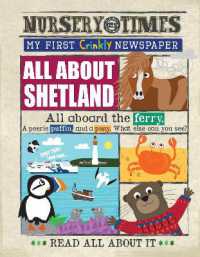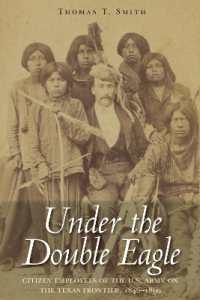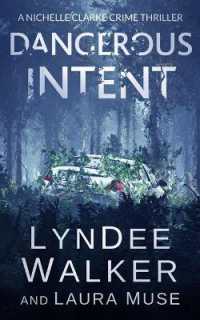出版社内容情報
遊園地で迷子、消える入れ歯――日々起こるユーモラスな不測の事態、そして最期まで保たれた愛情。認知症の父親と一家をめぐる物語。
帰り道は忘れても、難読漢字はすらすらわかる。
妻の名前を言えなくても、顔を見れば、安心しきった顔をする――。
東家の大黒柱、東昇平はかつて区立中学の校長や公立図書館の館長をつとめたが、十年ほど前から認知症を患っている。長年連れ添った妻・曜子とふたり暮らし、娘が三人。孫もいる。
“少しずつ記憶をなくして、ゆっくりゆっくり遠ざかって行く”といわれる認知症。ある言葉が予想もつかない別の言葉と入れ替わってしまう、迷子になって遊園地へまよいこむ、入れ歯の頻繁な紛失と出現、記憶の混濁--日々起きる不測の事態に右往左往するひとつの家族の姿を通じて、終末のひとつの幸福が描き出される。著者独特のやわらかなユーモアが光る傑作連作集。
内容説明
帰り道は忘れても、難読漢字はすらすらわかる。妻の名前を言えなくても、顔を見れば、安心しきった顔をする―。認知症の父と家族のあたたかくて、切ない十年の日々。
著者等紹介
中島京子[ナカジマキョウコ]
1964年生まれ。2003年、田山花袋『蒲団』を下敷きにした書き下ろし小説『FUTON』で作家としてデビュー、野間文芸新人賞候補となる。2010年『小さいおうち』で第一四三回直木賞を受賞、2014年山田洋次監督により映画化される。同年『妻が椎茸だったころ』で第四二回泉鏡花文学賞を受賞。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yoshida
Yunemo
なゆ
Tui
修一朗